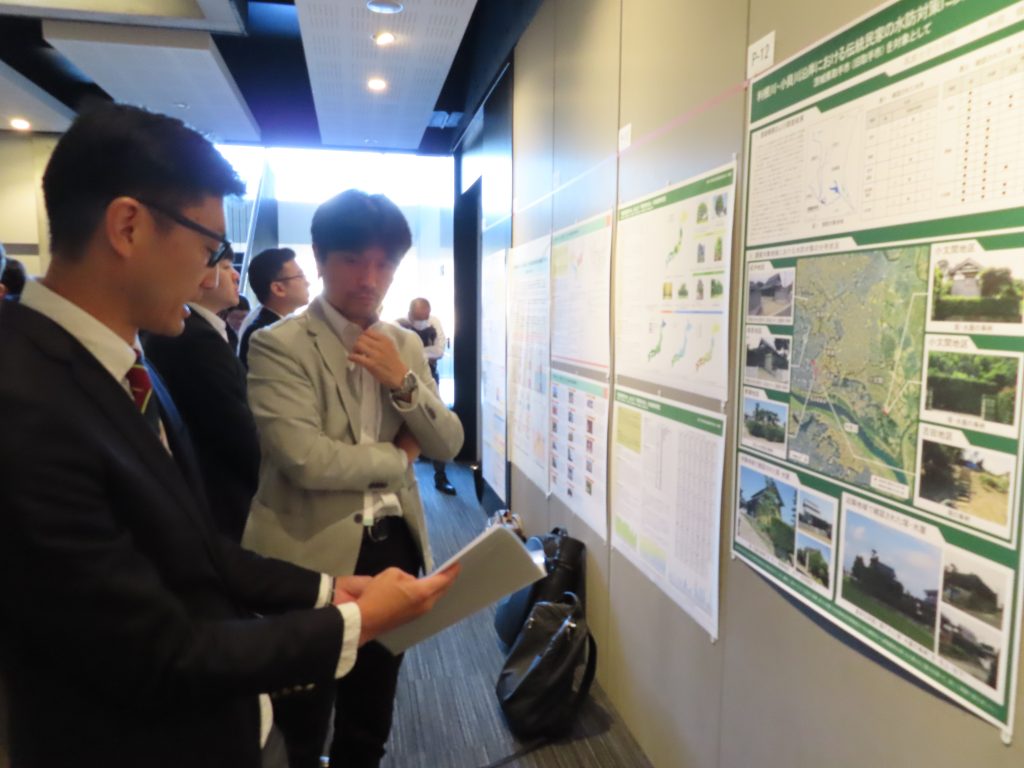室内温熱環境の実測調査の他にも、現地調査でわかってきたことがありました。
灰石の産地である臼杵市では、灰石を塀や基礎に利用している事例は確認できましたが、灰石のみかん小屋はみつかりませんでした。
海沿いの集落には漁業を生業としている集落が多いようですが、かつてみかんの栽培に力を入れていたという集落もみつかりました。
そこでは、漁業を営む集落の背後地にもみかん畑を広げていったとのことです。
調査中、みかん畑はあってもみかん小屋のない漁村集落がいくつかあって謎でしたが、ヒアリングで確認でき、納得。


そして、斜面地のみかん畑で見られるイヌマキは、やはり防風林のようでした。津久見で、イヌマキの生垣が連続するみかん畑を確認できました。

調査の最終日、津久見市では「軽トラ市」が開催されていました。
小雨の降る中、大勢の人たちで賑わっていました。
みかん小屋の調査も、将来的には何らかのかたちでまちづくりに貢献できるよう、頑張りたいところです。