静岡県焼津市の重要伝統的建造物群保存地区へ行ってきました。
明治以降に養蚕のほか、お茶やみかんの栽培を行っていた地域で、みかん小屋と思われる付属屋などが残っています。
斜面上の街道沿いに形成されているため、立派な石垣が積まれていました。
他ではあまり見たことのない開口部が気になりました。
旧街道がハイキングコースの一部になっているようで、平日にもかかわらず多くの中高年の方が歩いていました。








橋本研究室での研究活動を紹介します。
静岡県焼津市の重要伝統的建造物群保存地区へ行ってきました。
明治以降に養蚕のほか、お茶やみかんの栽培を行っていた地域で、みかん小屋と思われる付属屋などが残っています。
斜面上の街道沿いに形成されているため、立派な石垣が積まれていました。
他ではあまり見たことのない開口部が気になりました。
旧街道がハイキングコースの一部になっているようで、平日にもかかわらず多くの中高年の方が歩いていました。








この度、「人間-生活環境系学会 論文賞」を頂戴し、福岡での人間-生活環境系シンポジウムで授与式がありました。
また、受賞者講演をさせて頂く機会を設けていただきました。
受賞した論文は私一人の力で成し得たものではなく、多くの方々に支えられて調査を遂行し、執筆することができたものです。
講演の冒頭では、その御礼と感謝の気持ちを伝えさせていただきました。
今後は、これまで以上に研究を頑張らねばと、気を引き締めて努力する所存です。
【受賞論文】
橋本 剛、栗原広佑
対馬における群倉の配置に関する小気候学的研究
人間と生活環境、第29巻、第1号


第47回 人間-生活環境系シンポジウムに参加してきました。
会場は福岡女子大学。
公立大学も立派なキャンパスでした。
発表演題は、
ミセ造りの現存する漁村集落における夏季の小気候観測
でした。
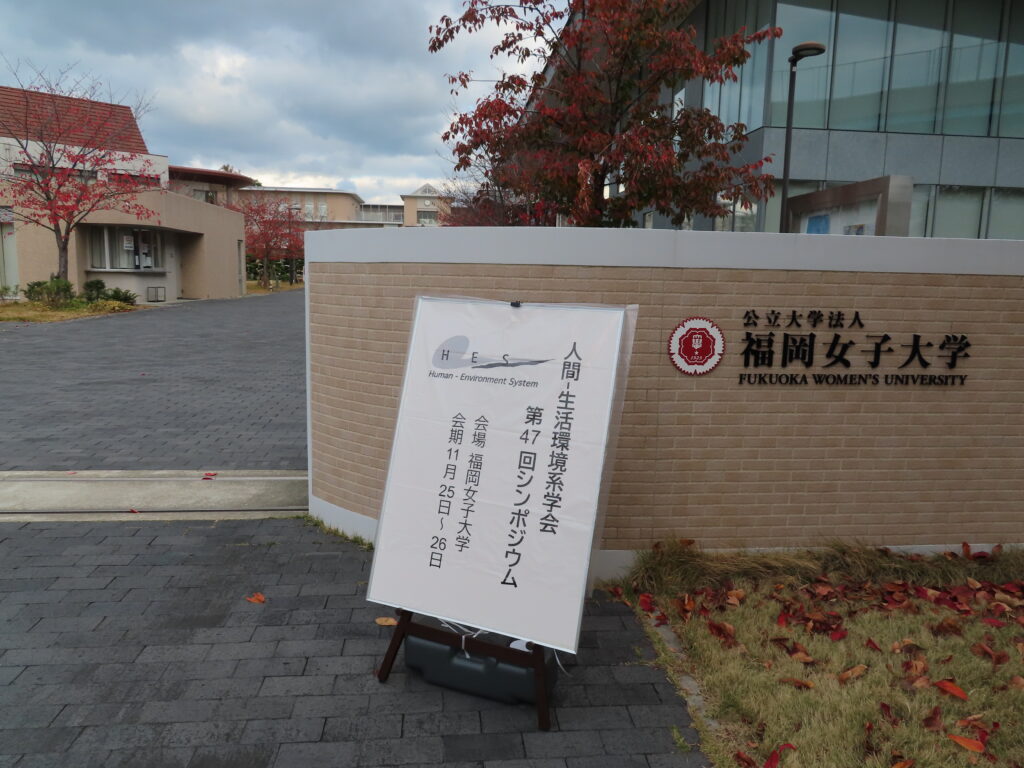

第62回 日本生気象学会大会(愛知)に参加してきました。
会場は日本福祉大学 東海キャンパス。
学会に行くと毎回感じますが、私立大学のキャンパスはどこも立派です。
発表演題は、
夏季における「ミセ造り」に形成される温熱環境
でした。


少し前のお話です。
島根大学の小林先生と、徳島県の山間集落などの調査に行ってきました。
重伝建の落合集落をはじめ、斜面集落が点在しています。
かつては葉タバコ栽培や養蚕を行っていたとのこと。
干し柿が有名な集落も。






2023年度日本建築学会大会(近畿)に参加してきました。
今回の会場は京都大学。
京都大学へ行くのは初めてのことでした。
3年ぶりの対面開催。
やはり対面の方がディスカッションが活発な気がします。
2日目午後の農村計画のオーガナイズドセッションが面白かったです。

今回は、奄美群島の与路島などへ行ってきました。
与路島へ行くのは今回が2回目。与路島へ泊まるのは今回が初めてでした。
同行者は名城大学の石井先生。
石井先生は日傘(晴雨兼用)も持参して、日焼け対策バッチリ。
私は、いつもながら成るようになるスタイル。
基本的には晴れているものの時々スコールのような激しい雨が降るお天気で、石井先生の準備が正解でした。
奄美は8月下旬がお盆の様で、フェリーの出港時刻が異なっていたり(島民の方のお話では1週間ほど前に決まったらしいです)、波が高かったのか風のせいかはわかりませんがフェリーの航路が異なって予定より時間がかかったりしましたが、いろいろと結果オーライな感じでした。
与路島のサンゴの石垣、見事でした。










長崎県の対馬に調査に行ってきました。
今回は東北工業大学の栗原先生との合同調査でした。
主には椎根の群倉で温熱環境の実測調査を実施してきました。
今回も住民の方々のご協力があってこそ実施できた調査です。
お天気は2勝1敗。
事前の天気予報では全敗もあり得たので、まずまずでしょうか。
また来年もよろしくお願いします。


徳島県に調査に行ってきました。
今回の調査は、大同大学・渡邊先生、名城大学・石井先生、東北工業大学・栗原先生との合同調査でした。
台風6号の動きによっては、行けない、帰れない、何もできない・・・という状況も心配されましたが、トラブルに遭いながらもなんとか最低限の調査は実施できました。
詳細は書きませんが、今回のトラブルからは大事なことを学んだ気がしています。
調査については、来年への宿題も残りました。来年は晴れるといいな。



愛媛県に調査に行ってきました。
今回は、島根大学の小林先生と一緒でした。
これまであまり知らなかったのですが、愛媛県にも魅力的な研究対象が沢山あり、驚いたり、嬉しかったり、ワクワクしたり。
伝統民家や伝統集落については、書籍やインターネットで手にすることができる情報がかなり整ってきている気がします。
一方で、残念ながら一部の保存対象を除くと総数的にはかなり減少しているという現実もあります。
でも、広く世間に知られていないものが、まだまだあるのだなと実感しています。
いや、私が勉強不足、経験不足なだけかもしれませんが。




