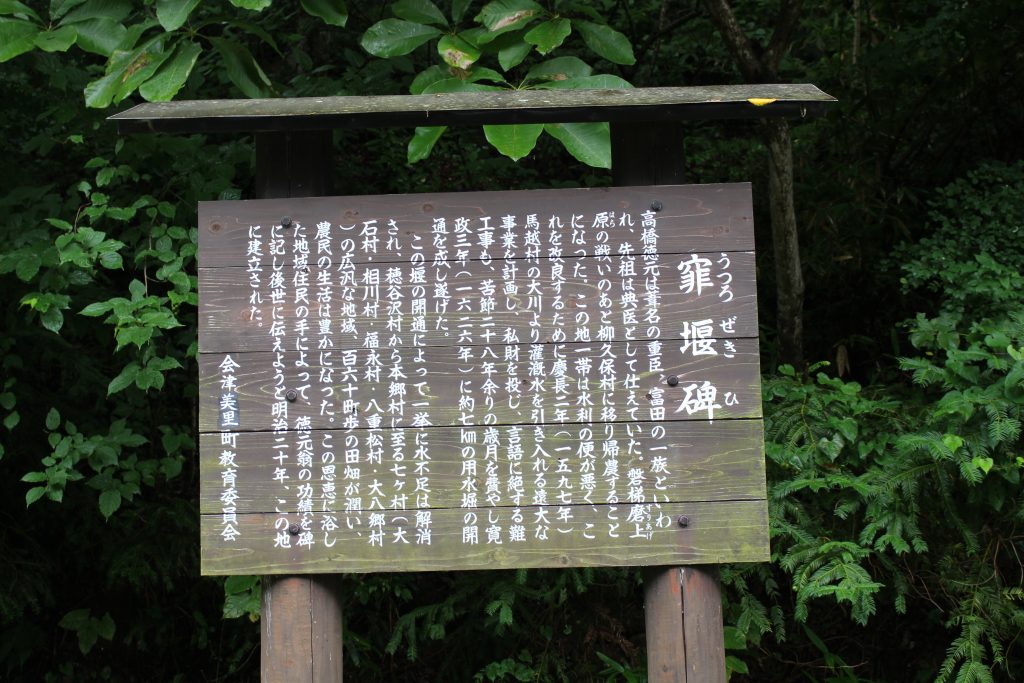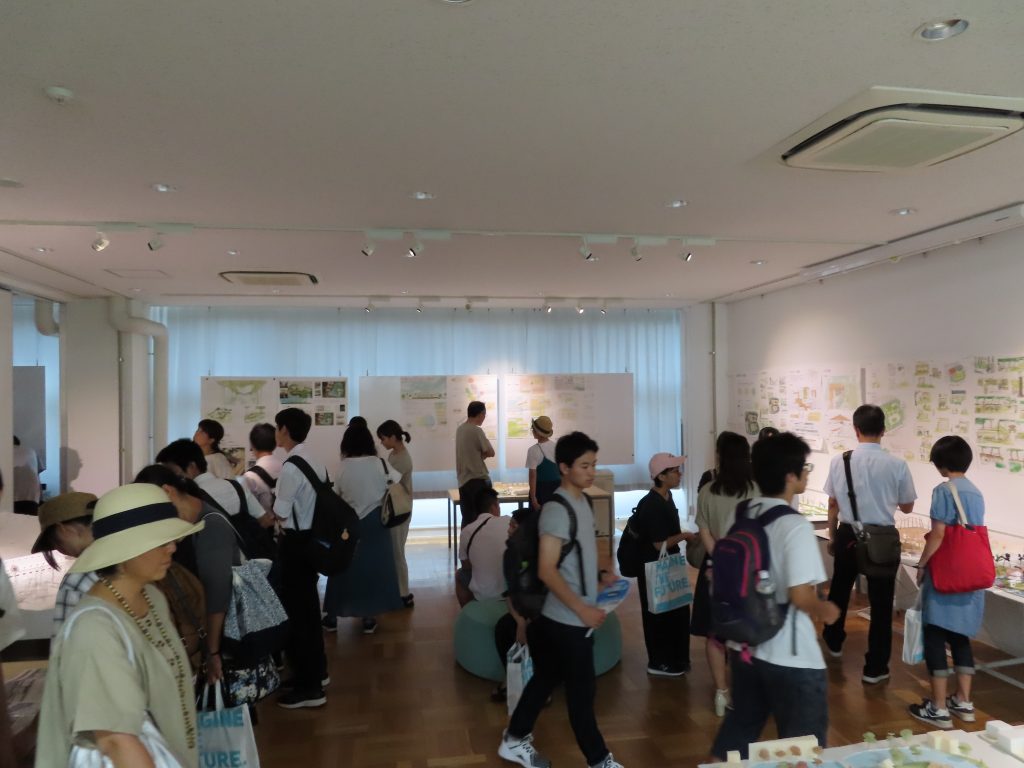津久見調査の追記です。
前回の報告から、だいぶ時間が経ってしまいました。
今回の調査でも、「かつてのみかん畑」を歩きました。
遠くから見ると杉林や雑木林の様に見える山の中に入っていくと、苔生した石垣の段々畑に遭遇します。
昨年度に同じ様な光景を目にした時は、フォトジェニックな場所だな〜としか感じませんでした。
今回はもう少し深く考えることができ、石垣の段々畑に木々が生えることにより、斜面の保水力が上がるとともに崩れにくくなるなど、防災の効果があるのではないか・・・と想像しながら調査していました。
一方で、手入れが行き届かず、石垣が崩壊して危険な状態になっているところもありました。
みかん畑がなくなった斜面地の石垣を保全・補修する意義が多面的にありそうです。
その他にも、防風垣の跡や山の上部に開拓されたみかん畑など、あらたな発見もあった調査でした。