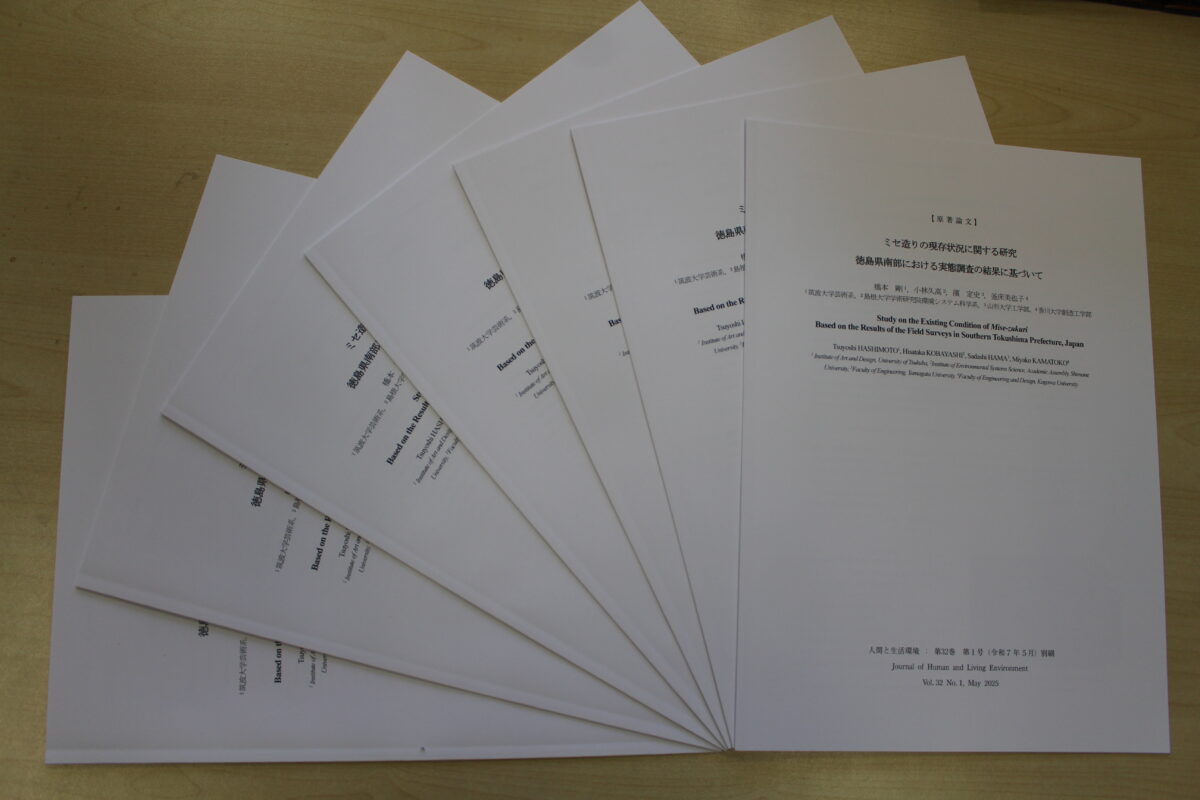昨年末と先週末に四国へ茶堂の調査に行ってきました。
2025年12月は安田女子大学の小林先生と愛媛県へ。
2026年1月は熊本県立大学の栗原先生と高知県へ。
まずは愛媛県。西予市を中心に茶堂を探して右往左往。
既存の資料があるものの、市町村合併前の旧住所のデータ、そして旧道と現道との照合・・・苦労しました。
四国はどちらかと言えば南国のイメージですが、山間は寒く、残雪がちらほら。
しかし、かなりの数の茶堂が現存しており、全てを見ることは出来ませんでした。
また、斜面に形成された石垣が凄い。一見すると狭い段々畑でも、初和の時代に工事が行われ、これでも昔よりは広く、なだらかになったということを、住民の方に教えてもらいました。よく見ると、耕作放棄地となった昔ながらの極端に幅が狭く急峻な石垣を見つけることが出来ます。
ぜひ、再訪したい。
そして、高知県。
なんと最強寒波が。そして、雪が降る・・・降り積もる。ここは四国?東北の間違いでは??というような風景の中、粛々と茶堂の調査を行いました。
集落の人々の集いの場であり、旅人をもてなす場であった茶堂。現代にこそ、茶堂が必要なのではないかと考えました。ご近所の人が集い、語らう、来訪者と触れ合い、交流する・・・そんな心と時間の余裕が現代人にはあるのかな、と。