橋本研究室の修了生である東北工業大学・講師の栗原広佑先生が、「人間-生活環境系学会奨励賞」を受賞し、第46回人間-生活環境系シンポジウムで授賞式がありました。
受賞した論文は栗原先生が博士後期大学院生として当研究室に在籍中に取り組んだ研究内容です。
受賞論文題目「山形県最上郡金山町における地域型住宅と薪ストーブ使用住宅の実態調査 森林資源の建材・燃料としての利用に着目して」


研究室ゼミで行った内容の紹介です。
橋本研究室の修了生である東北工業大学・講師の栗原広佑先生が、「人間-生活環境系学会奨励賞」を受賞し、第46回人間-生活環境系シンポジウムで授賞式がありました。
受賞した論文は栗原先生が博士後期大学院生として当研究室に在籍中に取り組んだ研究内容です。
受賞論文題目「山形県最上郡金山町における地域型住宅と薪ストーブ使用住宅の実態調査 森林資源の建材・燃料としての利用に着目して」


橋本研究室の修了生である東北工業大学・講師の栗原広佑先生が、「日本生気象学会 第31回研究奨励賞」を受賞し、第61回日本生気象学会大会(名古屋)で授賞式ならびに受賞記念講演がありました。
受賞した論文は栗原先生が博士後期大学院生として当研究室に在籍中に取り組んだ研究内容です。
受賞論文題目「薪ストーブ使用時に形成される居間の室内温熱環境の実測調査」


里山建築研究所の住宅見学会に行ってきました。
東日本大震災でいわき市に建てられた板倉構法の応急仮設住宅を移築再生したものです。
建材・設備機器等の9割以上を再利用したとのこと。すごいです。
製材の端材を活用した外壁も味があって素晴らしかったです。




大同大学・渡邊慎一教授の研究室、名城大学・石井仁教授の研究室と合同卒論中間発表会を行いました。
今年度はコロナ禍ということで、研究の進捗状況も踏まえ、例年よりも時期を少し遅らせての開催となりました。
そして、初のオンラインでの開催でした。
開催にあたってはいろんな議論があり、一時は今年も中止もやむなしとの意見もありましたが、オンラインで開催することができてよかったと感じています。
なにより、発表した学生たち自身が、これを機会に研究を積極的に進めることができたと実感できていると思います。
橋本研究室の発表は以下の通りです。
水畑日南子さん:大分県津久見市におけるみかん小屋の景観に関する研究
伊藤梨沙さん:庭の構成要素としての水塚の植栽 小貝川下流域を中心として
浦川京子さん:(仮)都市のヒーリングスポットの提案
(発表順)

ようやく2020年度の第1回のゼミを行いました。
もちろん、オンラインで。
どうなることかと思いましたが、なんとかなるものですね。
まずは研究室のみなさんの近況を確認。
みなさん元気そうでなによりでした。
次に、当座の「やるべきこと」「やれること」を確認。
この状況下でも何もできないわけではないです。
そして、研究室メンバーで取り組むことにしたコンペの方針を確認。
新たなチャレンジもはじまりました。
9月28・29日に六本木ヒルズでイノフェス(INNOVATION WORLD FESTA 2019)がありました。
そのイベントの一つに「つくばイノベーションテラス」があったのですが、展示空間デザインに研究室の大学院生、栗原くんと伊藤さんが参加しました。
橋本は展示空間デザインの監修を依頼されました。
「彩森の環境・TSUKUBAから生まれる最新のイノベーション」を展示空間のデザインコンセプトとして設定し、筑波大学キャンパス内で手に入れた枯れ枝や筑波山地の木材や緑を使用して空間を装飾しました。
「彩森(さいしん)」は橋本の造語です。
芸術専門学群の環境デザイン、建築デザイン、情報・プロダクトデザイン、クラフトなどの学生が装飾に関わっています。
主担当はデザイン専攻2年生の須永さん。
大変な仕事だったと思いますが、とても良くがんばりました。
なお、筑波山地の木材や緑は上林製材所のご協力を得て使用することができました。本当にありがとうございました。








先週末は京都府立大学で行われた「住まいと暮らしのデザイン研究 2019年度成果発表会」に参加しました。
大同大学・渡邊研究室、名城大学・石井研究室、京都府立大学・長野研究室、筑波大学・橋本研究室の学生が発表を行い、愛知産業大学・堀越先生も参加していただきました。
学生29名による25題の発表がありました。
学生からの質問も多くあり、ディスカッションも盛り上がりました。
浦川さん、水畑さんともに、ゼミでの発表練習よりもプレゼンが良くなっていて驚きました。
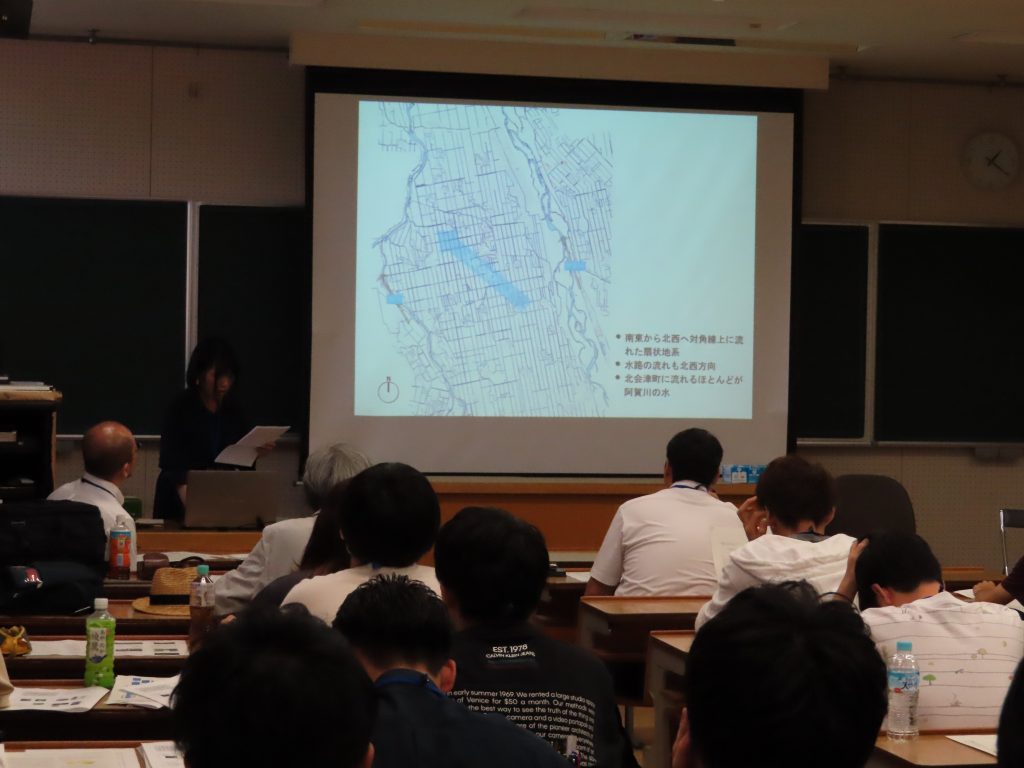


茨城県フラワーパークではバラまつりが開催中です。
研究室の伊藤さん、浦川さん、水畑さんの作品が展示されているとのことで、みんなで現地に行きました。
展示されている作品は、ミニチュアローズのジオラマ風の鉢植えです。




帰りには筑波山麓の地産材を取り扱う上林製材所さんのところで勉強させていただきました。

大学に戻った後は、通常通り、研究室ゼミを行いました。
みなさん、お疲れ様でした。
10月から延辺大学の高松花先生がゼミにゲスト参加してくれています。
先週・今週のゼミで、高先生の研究対象の一つである中国・延辺の井幹式民家について発表していただきました。
橋本研究室も、安藤研究室・藤川研究室らの合同チームの一員として、2011年の調査に参加しました。



昨日は研究室ゼミでした。
秋学期に向けて、ゼミのスケジュール調整等を行いました。
筑波大学では、春学期・秋学期の2学期制でカリキュラムが編成されています。
今年の秋学期は、学群4年生の伊藤さんの卒業研究を中心に、ゼミが行われる予定です。
筑波大学芸術専門学群デザイン専攻では、卒業研究として、卒論・卒制の両方に取り組みます。
最近では、卒論、卒制のどちらか一方にだけ取り組む建築系の大学が増えてきているようですが、やっぱり集大成として理論(研究)と実践(設計)の両方に取り組むことは大事なことだと思います。大変ですけど。
伊藤さんは、鹿児島県の加計呂麻島にある須子茂集落を対象地として卒論・卒制に挑戦中です。
