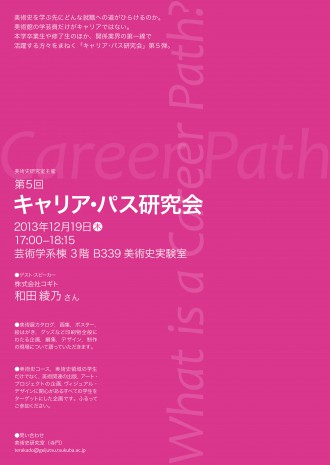修士論文発表会が開催されました
平成26年2月21日(金)、大学会館特別会議室において、平成25年度大学院人間総合科学研究科博士
前期課程芸術専攻の美術史領域と芸術支援領域の合同による「修士論文発表会」が開催されました。
6人の修了見込み学生が、2年にわたる研究の成果を発表しました。いずれも修士論文として質の高い
ものでしたが、本格的な研究は緒に就いたばかりと言えます。博士後期課程に進学する人も、新しい
環境で日々の仕事に向きあうことになる人も、 2年間で身につけたであろうめいめいの領域の学問的
方法論と研究対象に対する謙虚な姿勢をたいせつにして、いっそう出精されることを祈ります。
——————————
◆美術史領域
・赤間和美
「19世紀フランス装飾芸術をめぐる伝統と様式
―パリ万国博覧会(1900)における装飾芸術中央連合の展示館を中心に―」**
・喜代吉鏡子
「1910年代から1920年代の日本における洋画研究所と美術家の交遊」
・高橋翔
「《サモスのクーロス》―アルカイック期ギリシアにおける奉納彫像の巨大化」
◆芸術支援領域
・川村晃子
「美術館におけるファッション―教育普及活動を中心に」
・髙橋りほ
「アートプロジェクトにおけるNPO法人の役割に関する考察
―NPO法人向島学会を事例として―」
・中川三千代
「日仏芸術社の研究―展覧会活動と出版活動を中心に―」*
——————————
** 筑波大学芸術賞(修了研究・論文の部)
* 筑波大学優秀論文賞