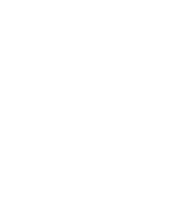| 取得年 | 氏名 | 博士論文題目 |
| 1991年 | 赤木里香子 | 自然観の変遷を指標とする美術教育の史的研究―1870~1920年代における描画教育と自然 |
| 1992年 | 石﨑和宏 | フランツ・チゼックの美術教育論とその方法に関する研究 |
| 1992年 | 宮脇 理 | 工芸による教育の研究―教育媒体としての可能性― |
| 1993年 | 遠藤敏明 | スロイド教育学研究―19世紀末からの歴史的展開と現代的意義 |
| 1994年 | 王 文純 | 中学校の美術鑑賞教育のカリキュラムに関する研究―台湾と日本の比較― |
| 1994年 | 向野康江 | 関衛研究―関衛(せき・まもる、1889~1939)と大正期芸術教育思想の展開― |
| 1996年 | 岡崎昭夫 | 現代アメリカにおける美術教育のカリキュラム開発に関する研究―ケタリング・プロジェクトとCEMRELの美的教育プログラム |
| 1996年 | 銭 初熹 | 中国の小学校における絵画教育の研究―日本との比較・考察― |
| 1996年 | 本村健太 | バウハウスの研究―社会的ダイナミズムとしての芸術教育― |
| 1997年 | 内田裕子 | V. ローウェンフェルドの造形教育理論についての研究 |
| 1999年 | 高橋敏之 | 幼児の人物描画における発達的変化と頭足人的表現形式の変異性 |
| 2000年 | 金 聖淑 | 韓国の美術教育学会の形成に関する研究―韓国における美術教育学の観点から― |
| 2000年 | 直江俊雄 | 20世紀前半の英国における美術教育改革の研究―マリオン・リチャードソンの理論と実践― |
| 2001年 | 丁字かおる | 学校美術教育におけるインターネット活用の基礎的研究 |
| 2001年 | 蔡 恵真 | 台湾の小・中学校の郷土教科における郷土美術教育に関する研 |
| 2002年 | 杉林英彦 | アビゲイル・ハウゼン(Abigail Housen)の美的発達段階論における測定方法を用いた鑑賞活動の評価法への実験的試行―美術館における鑑賞活動の事例調査を通して― |
| 2002年 | 張 東浩 | 韓国の近代化における美術教育の変遷 |
| 2002年 | 劉 素真 | 「国立台湾芸術教育館」の美術教育への貢献―事業の展開・「全国美術展覧会」の主催・機関誌『美育』の発刊を中心に― |
| 2003年 | 齊藤泰嘉 | 東京府美術館史の研究 |
| 2005年 | 和田 学 | 20世紀のアメリカ合衆国における美術鑑賞教育論の史的展開 : 「ピクチャー・スタディー」から「美術批評」へ |
| 2006年 | 小泉 卓 | 子どもの美意識の発達段階と多様性 |
| 2008年 | 土屋伸夫 | デザインギャラリー銀座・松屋の研究 : デザインギャラリー展の理念とその運営 |
| 2009年 | 韓 希暻 | 韓国のデザイン教育運動 |
| 2011年 | Rezende, Aline Lara | Curating experiences : the impact of curatorial practices on viewers’ engagement with contemporary art in museums |
| 2011年 | 奥村高明 | 美術教育における相互行為分析の視座―状況的学習論を基にした相互行為分析による指導法の改善― |
| 2011年 | 渡部晃子 | 米国における美術鑑賞教育の方法論―視覚的思考方略(Visual Thinking Strategies)の理論と実践― |
| 2011年 | Fondevilla, Herbeth Lim | Super postmodern : the influence of Japanese popular culture on Philippine contemporary visual arts |
| 2012年 | 牧野由理 | 明治期における幼稚園の図画教育の研究 |
| 2012年 | 太賀(畑中)朋子 | メディア芸術における実践コミュニティ形成に関する考察 |
| 2014年 | 市川寛也 | 妖怪文化の現代的活用に関する研究 : 地域住民を主体とする妖怪存在の再創造の事例から |
| 2016年 | 箕輪佳奈恵 | モルディブ共和国の初等美術教育とイスラム |
| 2017年 | 佐藤絵里子 | 1950~70年代のアメリカにおける美術教育評価論に関する研究 |
| 2017年 | 徐 英杰 | 中国の美術教員養成カリキュラムに関する研究 |
| 2017年 | 太下義之 | アーツカウンシルにおけるアームズ・レングスの原則に関する研究 |
| 2017年 | 中川三千代 | デルスニスと日仏芸術社-展覧会活動を中心に- |
| 2018年 | 有田洋子 | 戦後日本の教員養成大学・学部における美術教育学の人的制度基盤の成立過程 |
| 2019年 | 吉田奈穂子 | シュタイナー学校における造形教育の特質とその展開 |
| 2022年 | 廖 曦彤 | 美術のワークショップ実践者の学びに対する支援の研究―実践知とA/r/tographyの観点に基づいて― |
| 2023年 | 劉 栓栓 | 美術鑑賞教育における省察的学習を促す教育方法に関する実践的研究―中国の中学生を研究対象として― |
| 2025年 | 秋田美緒 | 美術科教育と地域美術館 活動を両立 させる アーティスト・イン・スクール事業―地域行政組織の内部人材が果たす事業コーディネイトの視点から |
| 2025年 | 森田 亮 | 肢体不自由特別支援学校における美術科カリキュラムの設計に関する研究─「逆向き設計」論を理論的背景とした設計枠組みの開発 ─ |