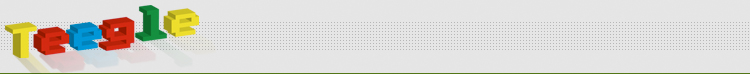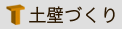
土壁の機能・特性
吸放湿性があり、多孔質材料である土壁は、空気中の湿度が高いときには水分を吸い込み、乾燥状態になると放出して室内の湿度・温度を保つ働きがある。また、真夏の暑いときには壁内の水分を外部に蒸発させる性質を持っている。このときの気化熱で室内が冷やされ、涼しい環境がつくり出される。土壁作りの手順
1 − 土を用意する。解体時に崩した元 の土壁に、藁を混ぜてよく練る。(古い土は多くバクテリアを含んでいるので新しい土を早く発行させるためにも貴重)

2 − 土壁の土台となる竹木舞を作る。竹の棒の先を削って細くし、組渡す準備をする。

3 − あらかじめ柱にあけておいた穴に先ほどの竹の棒を差し込んで、竹木舞を組む。縄でしばり、固定する。

4 − 竹木舞の上に土を塗る。内側、外側の両方に塗って乾燥させる。乾燥には夏期で2週間、冬期で1ヶ月。上塗りを重ねて約6ヶ月かかる。

5 − 完成。
体験記
日程:10月15日(土)、16日(日)、22日(土)、23(日)
時間:10:00〜15:00
協力:石野隆(壁作り職人)
10月15日(土)、16日(日)、22日(土)、23(日)の4日間、古民家の壁を完成させる壁作り体験が行われました。あいにくほとんどの日程で天気が悪く、撮影を行った16日も曇り。それでも当日は2組の体験参加があり、壁作り職人の石野さんに指導してもらいながら楽しそうに作業をしていました。
壁素材として土を使うのは日本の民家の伝統的な手法。土壁には吸放湿性があり、多孔質材料である土壁は、空気中の湿度が高いときには水分を吸い込み、乾燥状態になると放出して室内の湿度・温度を保つ働きがあります。また、真夏の暑いときには壁内の水分を外部に蒸発させる性質を持っており、このときの気化熱で室内が冷やされ、涼しい環境がつくり出されます。
この古民家では解体した旧豊島邸の土壁を再利用し、これに土や藁を加えて丁寧に練り上げたものを使用しています。今回は土を塗る土台となる竹木舞作りも体験の一環。竹木舞はちょうど網戸のように縦と横に竹の棒を走らせ、縄で固定したもので、これに土を塗っていくわけです。まずは石野さんが材料と手順を説明。コテを使ってしっかりと土を壁に塗り付けていきます。
2組の参加者はそれぞれ土壁塗りと竹木舞作り班に分かれ、初めての壁作りがスタート。慣れない作業ながら、皆さん上手に作業を進めていました。土壁作りには男性と女性の3人グループが挑戦。思っている以上に土を塗る作業は体力がいるようです。木舞作りにはお母さんと女の子二人。なかなか器用に仕上げていきます。
一つの壁を塗り上げるのにおよそ 時間。こうして乾燥と、上塗りを重ねて完成です。
|