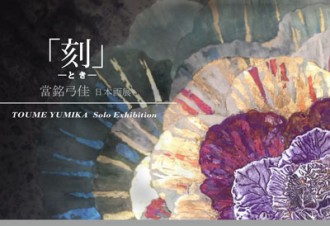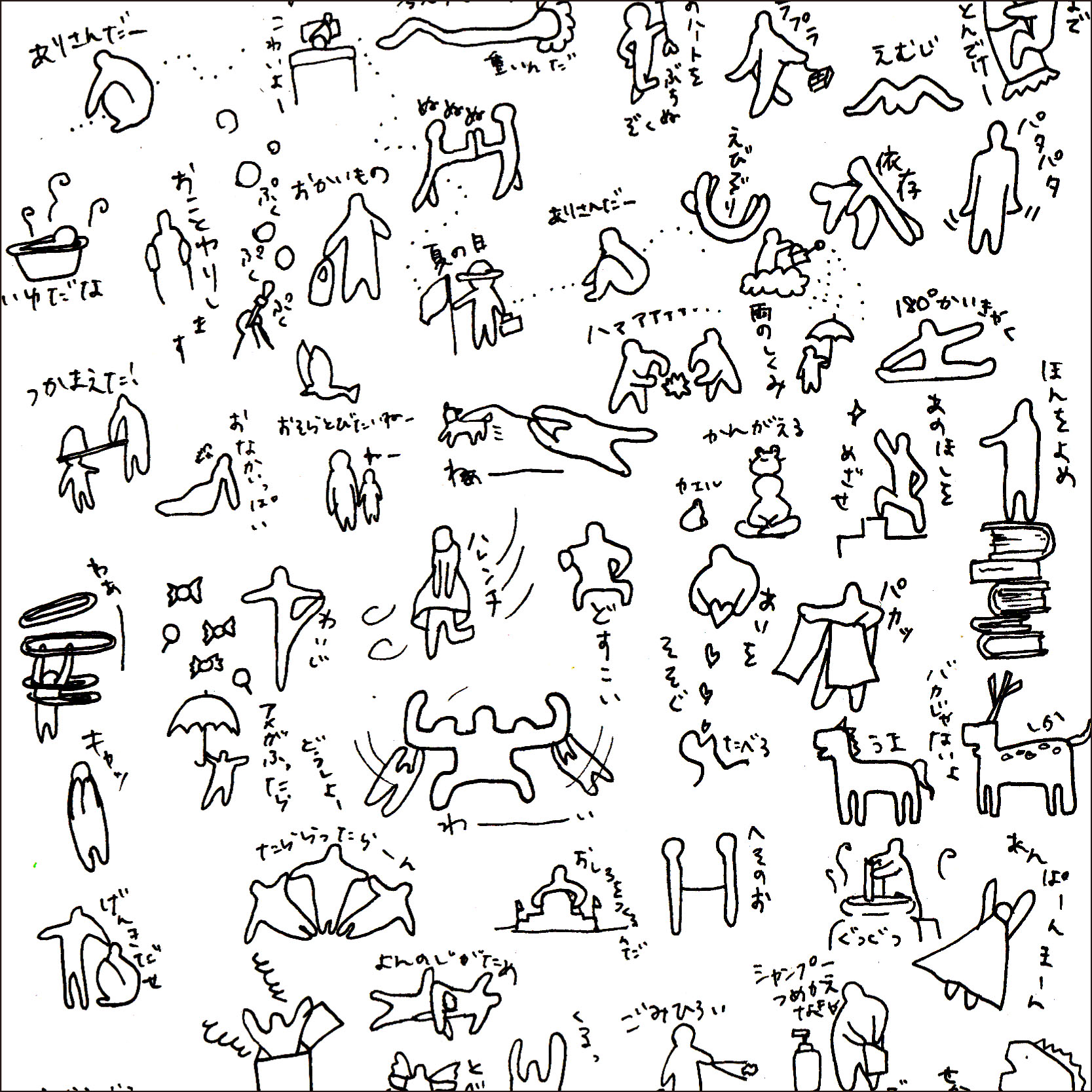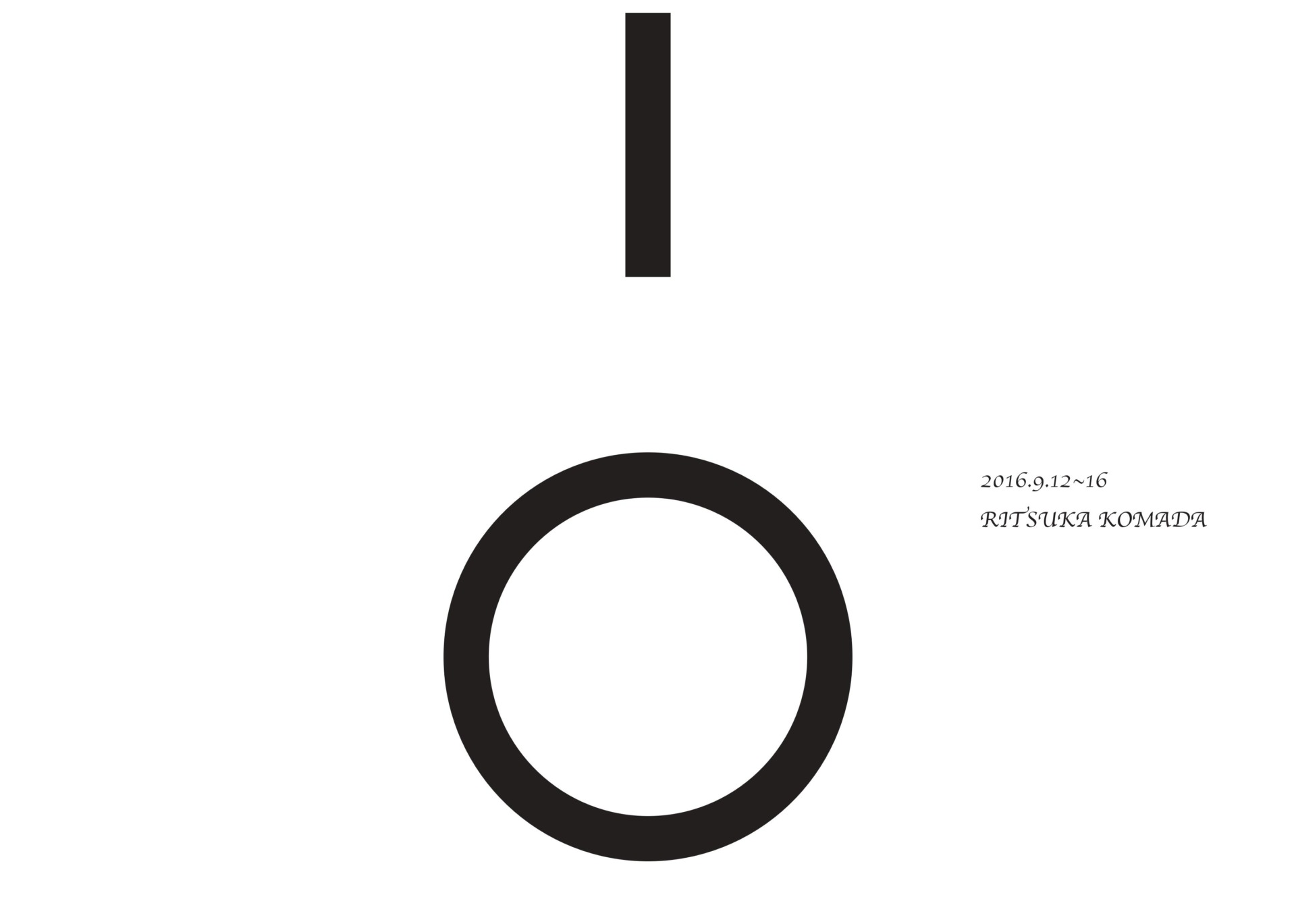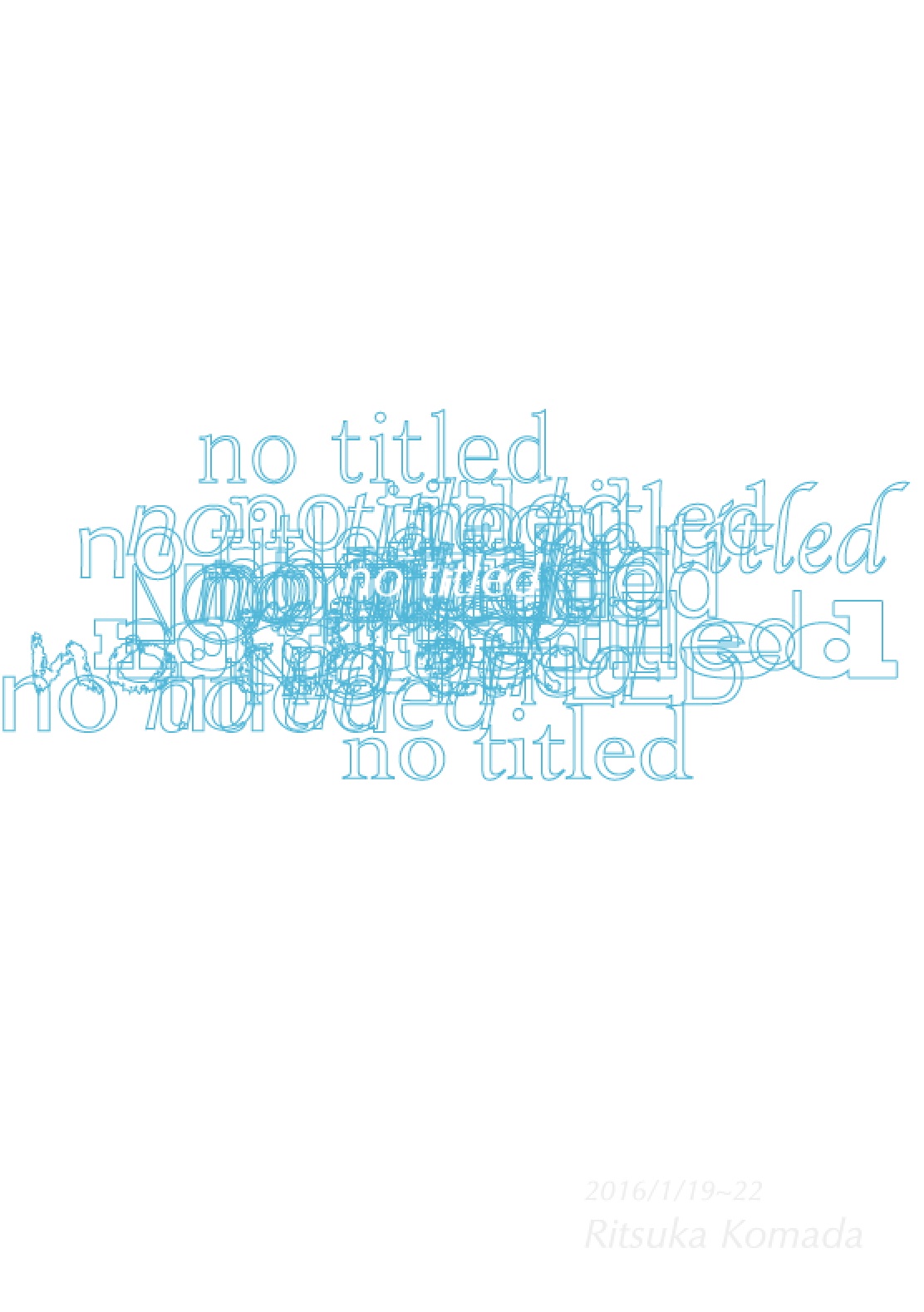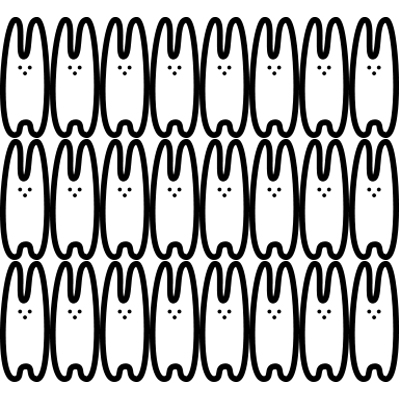「刻」當銘弓佳 2014年1月14日~2014年1月16日
展覧会「刻」が開催されます。
会場:アートギャラリーT+
会期:2014年1月14日(火)~2014年1月16日(木)
出展者:當銘弓佳(人間総合科学研究科芸術専攻日本画領域2年)
会場:アートギャラリーT+
会期:2014年1月14日(火)~2014年1月16日(木)
出展者:當銘弓佳(人間総合科学研究科芸術専攻日本画領域2年)
日本画作品を展示します。生と死。巡ること、流れること。絶え間ない刻(とき)の一瞬をテーマに。
確かな息遣い、湛える煌めきを探るように描ければ、と思います
T+review
日本画とは一言で形容しがたい分野だ。「日本画」という言葉自体が明治時代に海外から持ち込まれた「西洋画」と日本独自の芸術を分けるためにつけたためでもある。一般的に日本画と言われれば水墨画や美人画、花鳥風月などといった画材、主題を連想するだろう。うす塗の淡い色彩、墨の濃淡、開け放たれた空白・・・しかし、彼女の展示はそんな一般的に思われがちな日本画の世界とは一風変わったものだった。
生と死、そして流れ巡る絶え間ない「刻」をテーマに制作された作品たちに圧倒された。重厚な岩絵の具の重なりと、その余韻は鑑賞者に心地のいい印象を与える。
岩絵の具の最大の魅力は重なり合う砂の深みと、光に当てられ煌めく粒子であると考える。イメージで抱かれる日本画と現代日本画は大きな隔たりが生まれたのには理由がある。その理由が生まれた原因は、新たに数多くの顔料が開発されたことにあるのではないかと考える。かつての日本画が墨の濃淡を生かし、空間表現を何故得意としたかというと、それは単純に使用可能な顔料の数が少なかったからだ。極端な言い方になってしまうが、限られた色の中でいかに表現するのかがかつての日本画の課題だった。それが現代日本画でも変わりはないといえる。対して、近代の技術を活かし作られた様々な顔料をいかに表現として昇華していくのかというのが現代日本画の課題ではないだろうか。
その大きく変わりつつある現代日本画の確かな息吹を、彼女の作品に感じた二日間だった。(太田夏希)