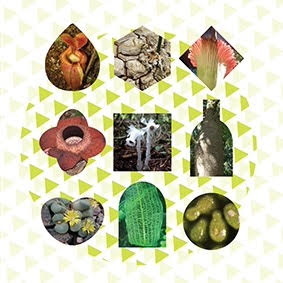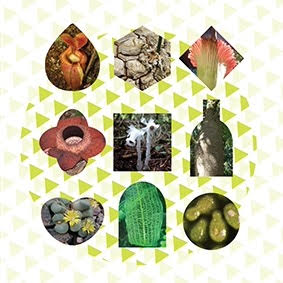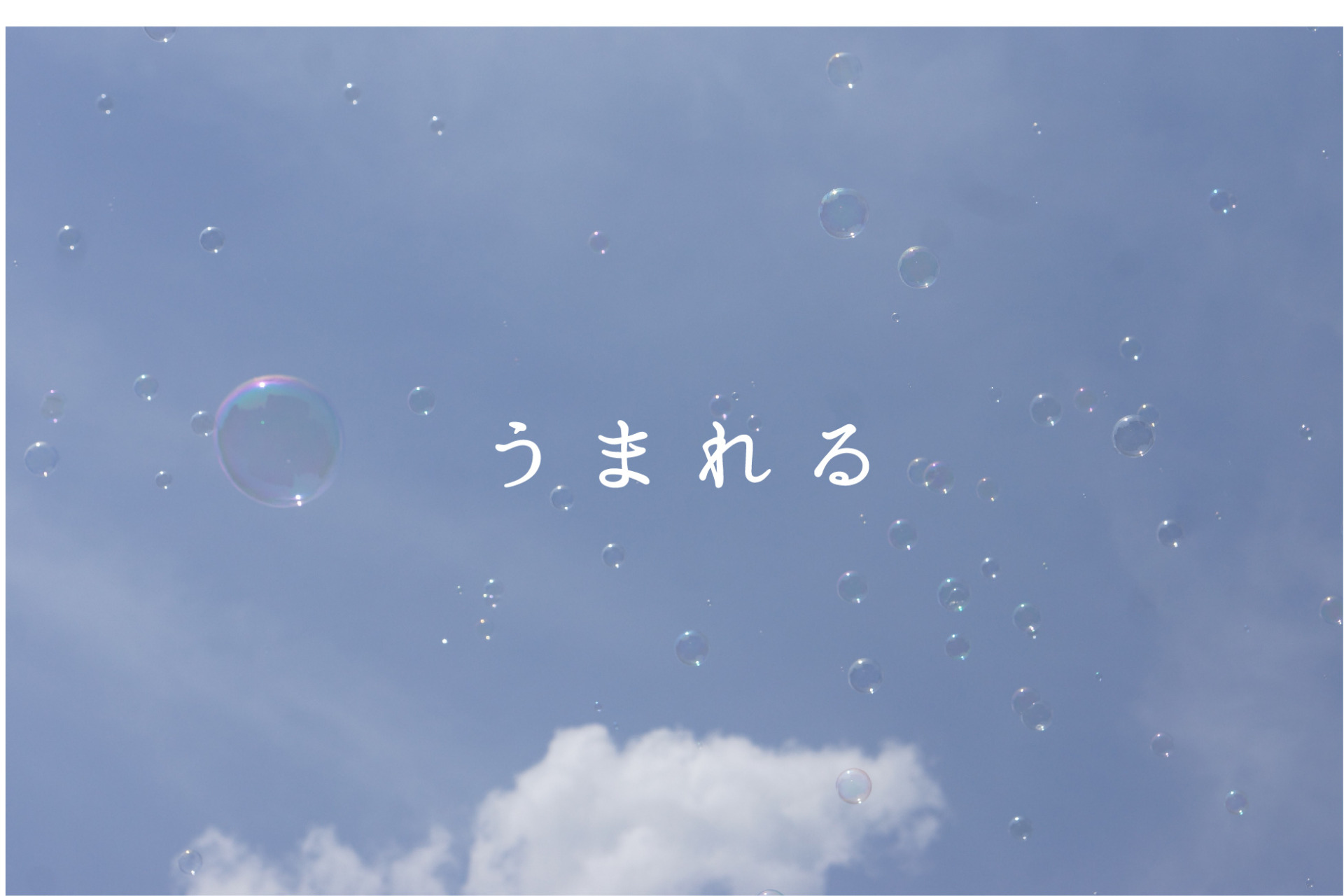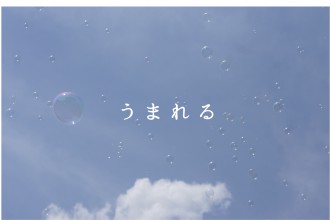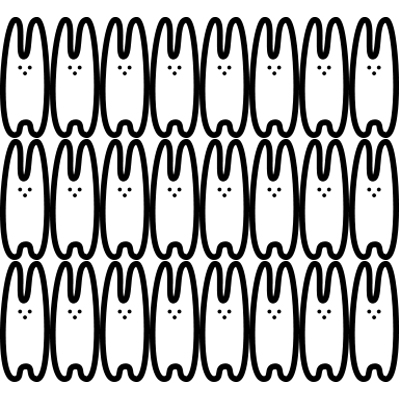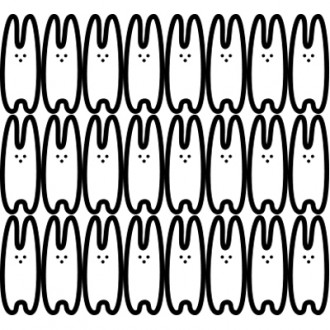「めずらしい植物展」久光真央、他2015年11月9日(月)~11月13日(金)
会場:アートギャラリーT+
会期:2015年11月9日(月)~2015年11月13日(金)
出展者:久光真央(芸術専門学郡芸術学専攻)
楊楊(情報デザイン修士2年)
遠山寛人(情報デザイン修士1年)
周ヨウ(情報デザイン研究生)
神田実咲(芸術専門学群情報デザイン領域1年)
ADP15(筑波大学アート・デザインプロデュース2015)のプロジェクトのひとつであるADPぷらんたが筑波実験植物園の企画展「めずらしい植物展」の主催の研究員の方と共同で制作したパネルを展示します。
T+review
外から見えるギャラリーの様子はいつもと少し違っていた。いつもの白いギャラリーが緑で埋め尽くされている。そこには小さな植物園が出来上がっていたのだ。
扉を開けるとやさしいオルゴールの音色が響いてきた。その音色に誘われて中へと足を踏み入れる。
背の低い植物の多くは机の上に、背の高いものは床に直接置かれている。中には天井から吊り下げられているものもあり、小さな空間だが様々なところに目を向けて楽しむことができた。展示されている植物にはそれぞれ手書きのカードが付けられていて「しっとりとした触り心地」「触るとニンニクのにおいがする」などの紹介文のとおり、ここに展示されている植物には実際に触れることでそれらの違いを感じることができる。柔らかな触り心地の白みがかった色をした葉を持つアサギリソウが印象的だ。
なかには世界最大の花・ショクダイオオコンニャクのように実物を展示できない代わりに等身大のパネルが展示されている場合もあり、それを見上げる、自分の身長と比べるなどでその大きさを十分体感できる。
一方、壁面には写真と漫画の2種類の解説パネルが貼られている。一枚には植物をアップで映した写真と短いキャッチコピーが付けられており、もう一枚は6コマ漫画だ。めずらしい植物の特徴を「まめくん」などの個性的なキャラクターたちがわかりやすく紹介している。
心地良い音楽と緑に囲まれた癒しの空間。そこではゆったりとした時間が流れていて、思わずずっととどまっていたくなってしまった。パネルからもわかるようにここで紹介されている植物たちは筑波実験植物園でも見ることができる。美術館だけではなく、ときどき植物園にも足を運んでみるのはいかがだろうか。(大藪早紀)