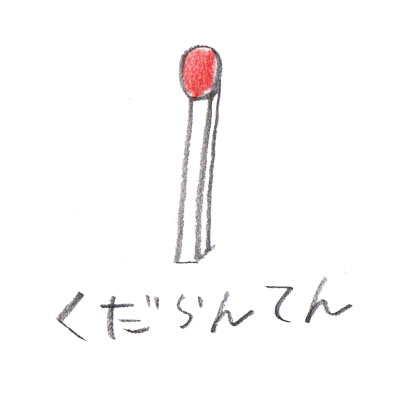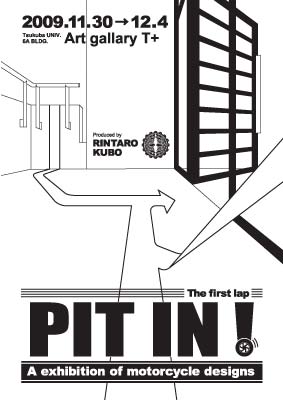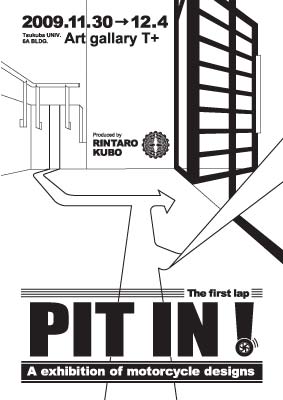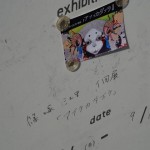「くだらんてん」 田中みさよ 2009年12月7日~2009年12月11日
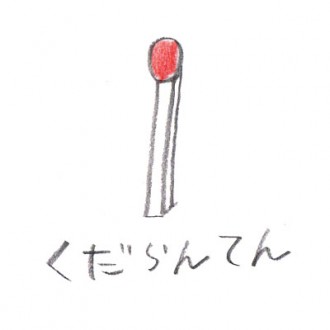
展覧会「くだらんてん」が開催されます。
会場:アートギャラリーT+
会期:2009年12月7日~2009年12月11日
出展者:田中みさよ(構成専攻2年)
くだらないことを、くだらない と切り捨てないこと。くだらないことかもしれませんが。
T+review
わたしたちは、昨日の授業中、風呂に浸かっているとき、眠りにつく前、いったい何について考えていただろうか。今になって思い出そうとしても、ぼんやりとして、なかなか思い出せない。わたしたちは(眠っているとき以外)一日中頭を使って何かを考えているはずなのに、何を考えているのかということについては案外うやむやである。わたしは今回の展覧会を見て、彼女の頭の中を覗いている感覚を覚えると同時に、自分は普段何を考えているのかということを振り返らずにはいられなかった。
クロッキー帳の紙を破って、ギャラリーの白い壁に無造作に貼り、鉛筆(と少しの色鉛筆)で、ユーモアに満ちた脱力系のらくがき(?)を描く。ギャラリーは拡大された彼女のクロッキー帳となって、そこには彼女が普段考えていること(「頭のもやもやを使ってマフラーを編めたらいいのに」)、思いついたアイディア(「イスと一体になれるイス」)、真摯なつぶやき(「こちらが意図しているかどうかがあなたにとって意味があるのかどうか」)がメモ(=記録)されている。「くだらんてん」というなんとも気の抜けた字面(展覧会名)はまさに内容を象徴していて、「くだらない」鉛筆でのドローイングが壁に貼られた紙を埋め尽くしている。冒頭のあいさつで「いろいろなことが、まだ、整理のついてないままです」とあるように、これは一個の完成した作品ではない。それよりもずっと前の段階、彼女の頭の中の吐露であって、わたしたちは彼女が普段どんなことを考えているのか、頭の中の混沌を覗いているような感覚(好奇心)を覚えるだろう。しかしやがて、自分自身は普段何を考えているのか、ということを考えずにはいられなくなる。おそらく、彼女もわたしたちもたいていいつも「くだらない」ことばかりを考えていて、わたしたちはあまりのくだらなさにすぐ忘れてしまうが、彼女は決して「くだらない」と切り捨てたりせずに、きちんと記録しておく。そこが両者の決定的な違いである。彼女は「くだらない」ものが秘めている未知なる可能性を知っている。たしかにひとつひとつは「くだらない」ものかもしれないが、その蓄積、あるいは化学反応によって新たなものが創造される可能性は無限大である。そういう意味で、「くだらない」ものとは決して「くだらない」ものではあり得ない。彼女の頭の中の「くだらない」ものが、いつかわたしたちの思いもよらぬものへと化けるときが待ち遠しい。(金沢みなみ)