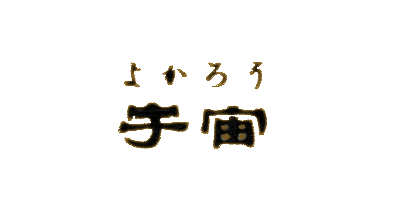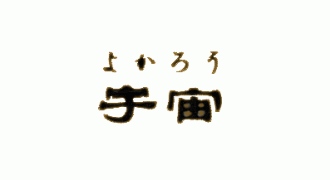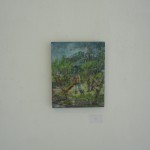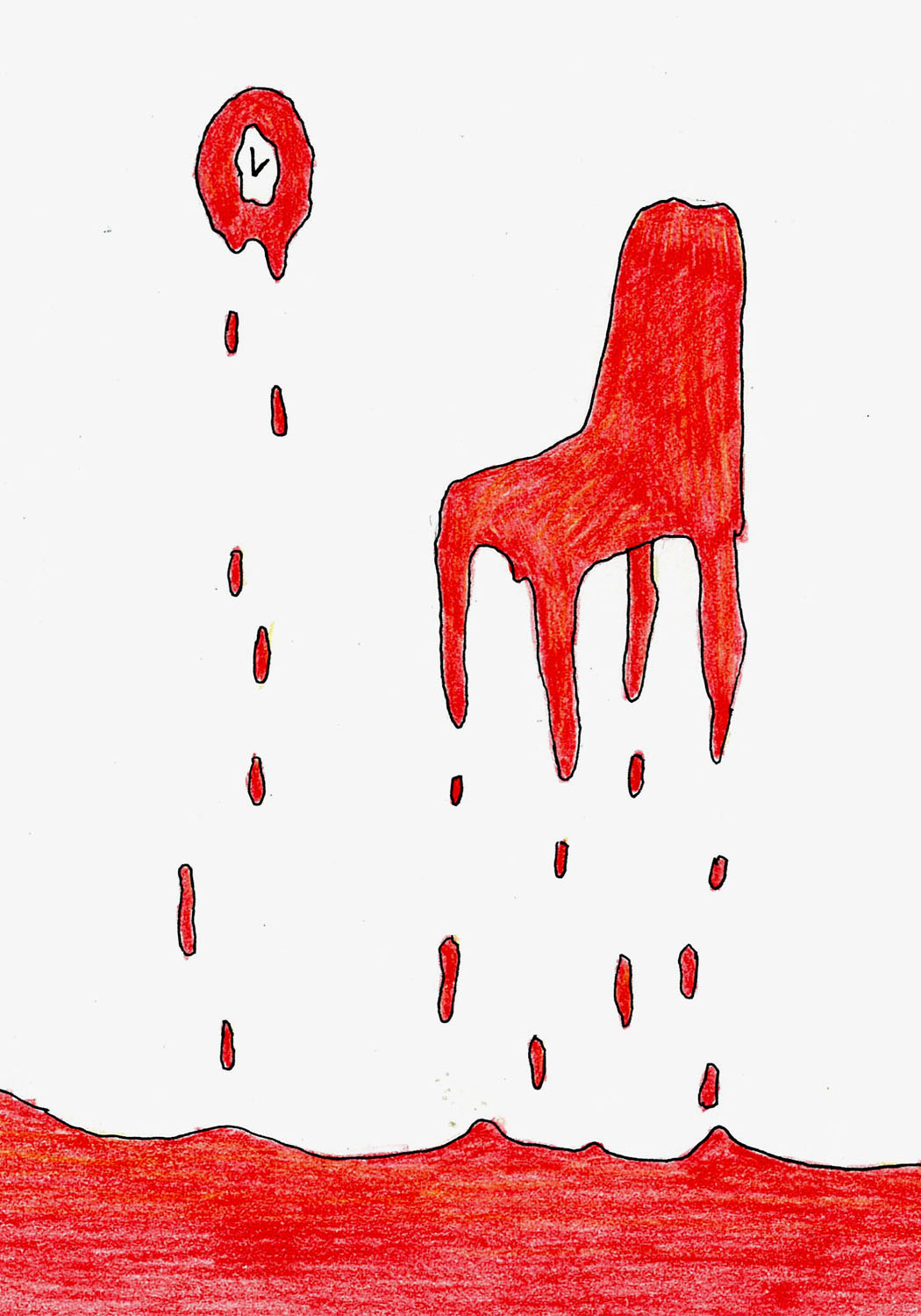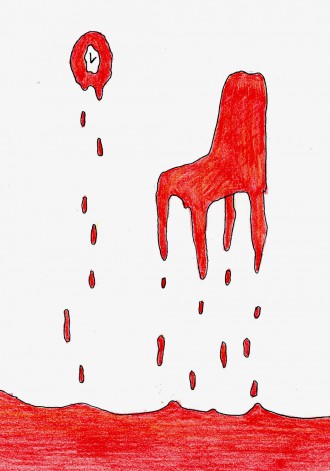「恋人」 藤田奈々子 2011年10月31日~2011年11月4日
会場:アートギャラリーT+
会期:2011年10月31日~2011年11月4日
出展者:藤田奈々子(芸術専門学群構成専攻VD領域4年)
写真の展示
T+review
ギャラリーに入ると、柔らかい光に照らされた沢山の写真たちが並んでいる。縦横の列や並びなどは関係なしに並んだ写真は、展示空間全体に動きを生み、いきいきとした印象を与えている。散り散りになっているこれらの写真は、浮かんでは消える頭の中のイメージのようである。「恋人」と聞いたときの心の様子を表しているのかもしれない。
作者はこの展示で、恋人の存在を示そうとしているわけではないだろうし、観る側にとってもそのような印象は受けない。感じるのは、写真という形で切り取られて作品群となった、「恋人」に関する多様なイメージ。そして彼に対する、幸せで、強い作者の気持ちである。作者は、恋人について浮かぶものを切り取り、カメラで時間を止めて作品としていく過程で、自分も恋人のことを再認識したかったのだろうか。
写真に写っているのは、恋人との生活の点景である。彼が写っているものあるし、風景の一部の写真もある。そしてカメラを覗く目線は常に彼女のもので、恋人をやさしく見つめているような視点や、彼と過ごしているときにぱっと見上げたような視点で撮られた木々などにより、彼女の存在を感じとれる。まるで自分が作者になったような気分になる。
自分の恋人を作品にすることは、もしかしたら勇気のいる行為だったかもしれない。主観が入りすぎてしまったり、見せ方が難しい部分もありそうだ。しかし、思い切って恋人のことを表現したこの展示は、その表現を肖像など、恋人を直接的に写すもののみに制限していないためしつこくなく、観る側にためらいを与えることもない。素直に作者の、「恋人のイメージ」が再現された展示だった。(岡野恵未子)