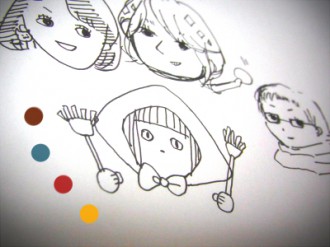「馬鹿な機械展」 土屋恒人、早川寛人、打田雅俊、私市瑞希 2013年1月15日~2013年1月17日
会場:アートギャラリーT+
会期:2013年1月15日(水)~2013年1月17日(金)
出展者:土屋恒人、早川寛人、打田雅俊、私市瑞希
(デザイン専攻3年)
あけましておめでとうございます。このたび私達「ねじクラブおまつり」はT+様のご支援を受けまして第一回物理博覧会「馬鹿な機械展」を開催する運びとなりましたのでお知らせ申し上げます。さて、私達が今回発表申し上げるのは「馬鹿な機械」ひたむきな機械達との触れ合いが行われます。火事にならないように気をつけます。(※実際には火事になることはありません)
T+review
誰もいないギャラリーの中は賑やかであった。部屋のどこにいても、ぎっちりと並んだ機械たちの発する音が聞こえてくる。首を振る扇風機の生む風音、次々に画面が切り替わるテレビの声、足踏みミシンの激しい音、アンケートボックスから聞こえるかすかな振動音。勝手に動いている機械たちもあれば、スイッチを押すなど私たちが何か働きかけることで動き出すものもある。彼らの機能は様々だが、共通していることもある。それは、彼らの動きが人間の要望・欲望に従った動きであるということ、そして、その動きしかできないということだ。
人間の要求に律儀に答えようと、与えられた役割通りに淡々と動く馬鹿共。しかし、その答えが常に完璧であるとは限らない。この展示ではその不完全さが垣間見える。例えば、“小せつ”“たつ巻論文”などの、単語の不自然な変換。また、展示された“小せつ”の中に出てくる「くるみですら」というフレーズの後には、「『くるみ』は名詞、『です』は丁寧語、『ら』は彼らのら」という、丁寧だが何ともトンチンカンな説明が挿入されている。壁にある「静かに」という張り紙は、執拗なまでに何枚も打ち出されている。
生真面目だけどもどこかずれている彼らの姿に、私たちはちょっと笑ってしまう。しかしその不自然さと同時に気味の悪さも感じはしないだろうか。なぜならその間違いはあまりに非人間的で、無感情だからだ。彼らは機械なりに頑張っている。自分に与えられた使命を淡々とこなしている。だが、当たり前ながら、彼らは自分のしている仕事が何であるのか、自分は失敗しているのかどうか、なんてことは考えていない。だから滑稽な、理解しがたい失敗をする。しかし、彼らを創り出したのは人間なのだ。人間の生み出したものが人間に理解できないような間違いを犯している…。
もちろん、この展示の機械たちの失敗は、意図的に演出されているのだろう。“小せつ”を見て、私たちは笑っていられる。しかし心の中では普段の生活での、機械との大小さまざまな不具合を思い出しているのではないだろうか。見過ごしてしまっているのかあるいは見ないふりをしているのか、普段深刻に考えることのない機械と人間との噛み合わなさを。(岡野恵未子)