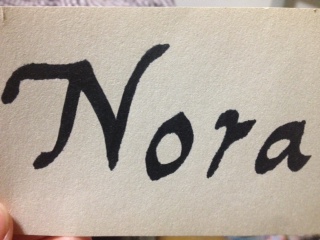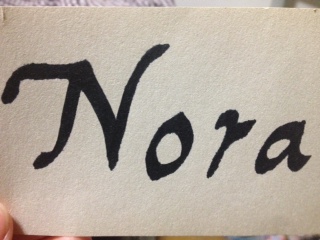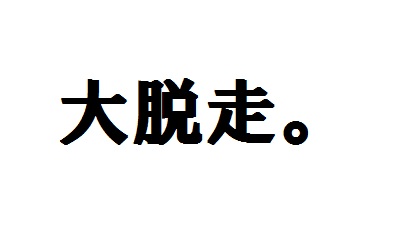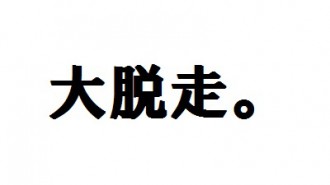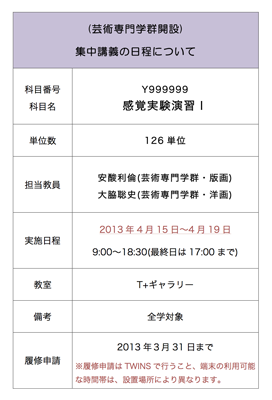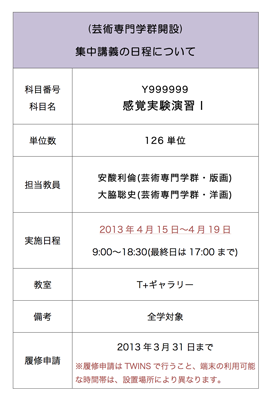「のら」 本江七緒 2013年4月30日~2013年5月2日
会場:アートギャラリーT+
会期:2013年4月30日(火)~2013年5月2日(木)
出展者:本江七緒(博士前期過程芸術専攻彫塑領域2年)
植物の絵と木彫のマグロを展示する予定です。3日間ですが、お越し頂けたら幸いです!よろしくお願いします!
T+review
繊細であるようで、ざっくばらんな光景がそこに広がっていた。
精密に描かれた? いや、その境界線も曖昧な、それでいてどこか不思議な絵とぼんと唐突に表れたマグロに視線を奪われ、思わずやられたと感じた。
この花、この木、この建物を・・・それらを一度目にしたことがあるような、ないような・・・記憶を辿るのだけれど明確に思い出せない。不思議。不思議。としか言いようがないのはもうお手上げだ。
しかしこのマグロ、生きていたことがあるのだろうか。不思議な絵に囲まれたなか異様なまでの存在感を放つそれはどうぞ切ってくれと言わんばかりの眼差しで、しかし、目を合わせてくれない。展示者の執着心でもあるような眼差しがリアルに感じられる場所と、ふっと気を抜いたような空気が同居する作品たちやその展示空間にふと不安を覚えてしまった。だが不安定ななかにも確かにヒトがつくったという温かみが残っていた。それを感じたとき、何故か「みんなちがって、みんないい」という懐かしい詩を思い出した。
この不思議な空間に同居する作品たちはみんなちがう。そうありながらなにかひとつの、なんと表現したらいいのかわからないが、おおきな流れのなかに、それは展示者という媒体なのだろうか、そういうなかに在るのだと、そう感じた。(太田夏希)