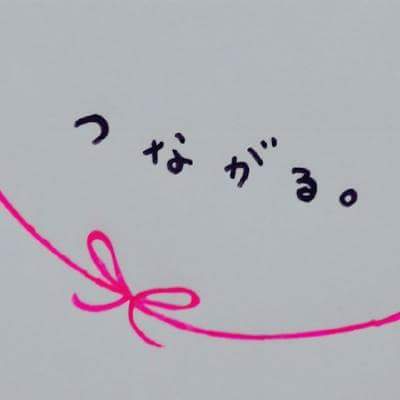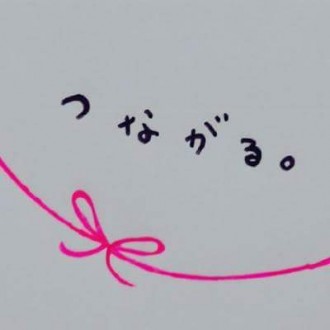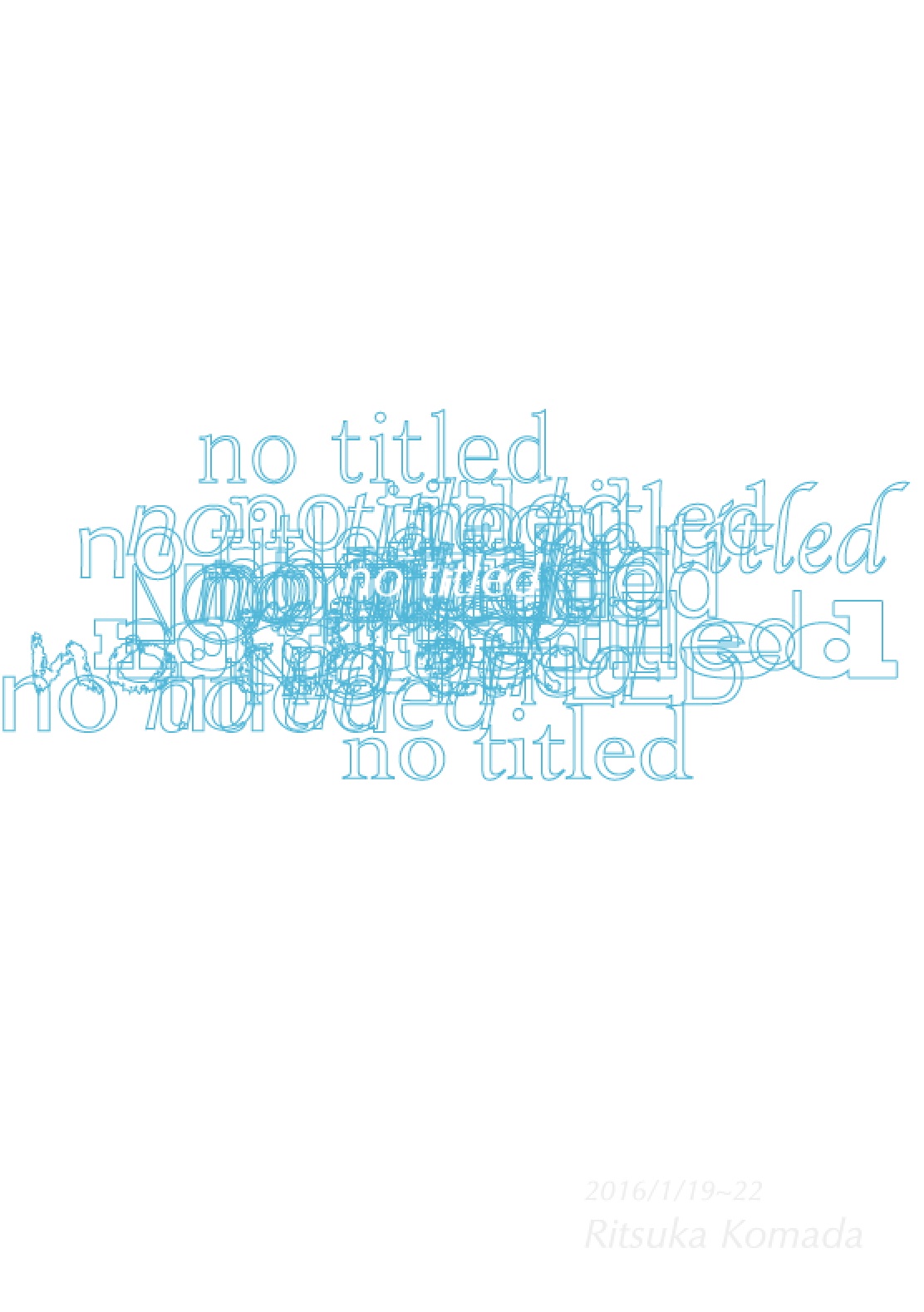「つながる。」石島朋佳2016年3月14日~3月18日
会場:アートギャラリーT+
会期:2016年3月14日-3月18日
出展者:石島朋佳(芸術専門学群美術専攻日本画コース、4年)
モデルを依頼、描く、
モデルに次のモデルを選んでもらう。
この繰り返しでバトンをつないできた
『モデルリレー』。
このリレーで出会った筑波大学の
学生さんを紹介します。(デッサン・日本画)
T+review
「一秒に一人のペースで誰かと知り合ったとしても、一生のうちに全人類と知り合いになることはできない。」という話を聞いたことがある人がいるかもしれない(そしてたいていこの後に『だから人との出会いは奇跡みたいなものである』と続くけれど、私はこの言い回しは個人的にあまり好きではない)。世界には70億人の人間がいるが、人の一生のうちではその中のほんのわずかな人間としか知り合うことができない。逆に言えば、世の中の何十億という人間は、お互いに見ず知らずの他人であり、普段は何の関わりもないただの有象無象の群衆なのである。
だからその群衆の中から、ひょいと急に一人の特定の人間の人格が浮かび上がってくると、広い砂浜の中から小さい貝殻を見つけたときみたいな、何とも言えない気持ちになる。今回の展示はそれに似たものが感じられた。たくさんの人物画の展示である。描かれた人は様々な学群の筑波大学の学生である。同じ筑波大学生であっても、普通であれば道ですれ違っても気にも留めないような、ほとんど縁のない人たちである。作者はそのような人たちに対して、絵のモデルというだけでなく一人の人間として、それぞれ真摯に向き合って作品を制作したのであろう。展示室内には作品の他にも、モデルをしてくれた人の紹介文が収められたファイルもおかれていて、作者の人間に対する関心の強さをうかがい知ることができた。
興味深いのは「モデルリレー」というモデル役の決め方である。モデルの人がその人の知人の中から次のモデルを選び、その次のモデルの人がまた選び……という風に次々とモデル役のバトンを渡していく方法である。これがそのままタイトルの「つながる。」にもなっていると思われる。一人の人間の持つ他人とのつながりは限られているけれども、自分の知人からさらにその知人へとどんどんつながりを伸ばしていくと、普段意識されないたくさんの人を知ることができ、そしてそれぞれ違った人格を持って日々暮らしていることに気づかされる。集団に埋もれがちな個を感じることができるよい機会であったと思う。(市川太也)