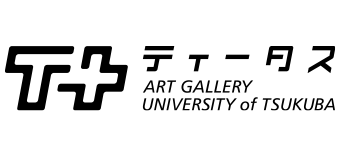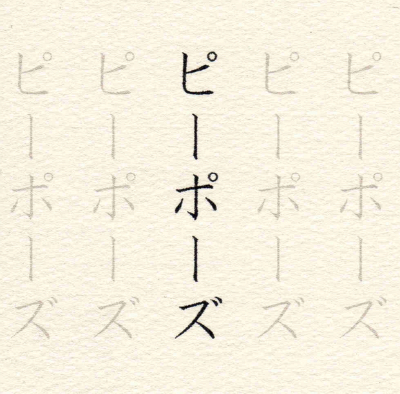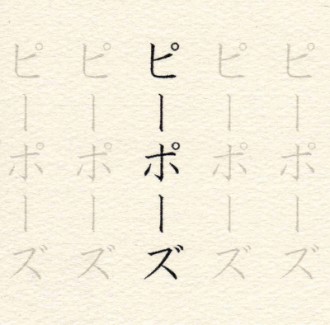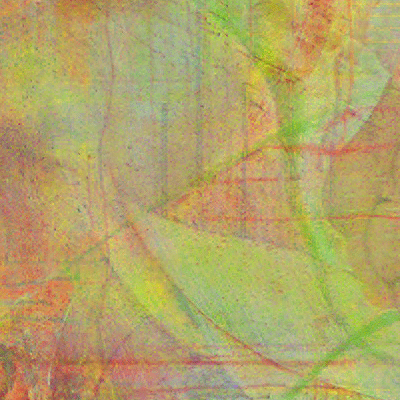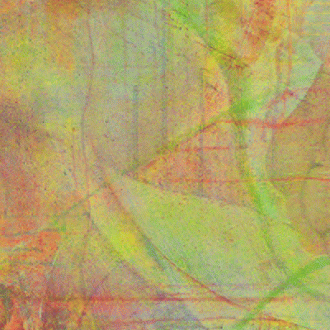「make up」 浅井佑子 2010年1月25日~2010年1月28日
会場:アートギャラリーT+
会期:2010年1月25日~2010年1月28日
出展者:浅井佑子
(博士前期課程芸術専攻総合造形1年)
化粧をテーマとした映像作品の展示。
T+review
大きな黒い瞳の中に化粧品・化粧道具の数々が映り込む、完璧に武装された女性の目がある。化粧品会社の広告のように、非の打ち所のないDMだ。
最近、日本が世界で二番目にコスメに投資していることを知った。とはいえ、資金の大半は宣伝に用いられているそうだ。宣伝には、えもいわれぬほど美しい女性達が抜擢され、素顔でも十分に美しいであろう顔に、さらに魅力的にみせるような化粧をする。桃のように滑らかな肌には、毛穴を消しより白く見せるおしろい。みずみずしい果実を口にした後のように潤った唇には、艶やかさや色を際立たせるリップスティック。奥ゆかしく透き通り今にも語りかけてきそうな瞳には、脇から演出するアイラインやつけ睫毛、アイシャドウ。といった具合に、例に暇が無い。商品は、次々により新しくより画期的なものに取って代わり、人々はより良い商品を求め、より進んだ化粧に挑戦する。
何の脈絡もなく綴ったように思われるここまでの話を、この私の頭に浮かばせたのは、他でもない展覧会「make up」である。マニキュアを用いたペインティングや、口紅を塗った唇を花のように見立てた作品もあったが、とりわけ衝撃を受けたのが、顔面の右目を含んで切り取った画面。その右目の瞳には、化粧をする人の動きが鮮明に映っている。すっぴんから始まり、目の縁ギリギリに黒いラインを入れ、睫毛を付け、また一層幅のあるラインを引き、幾重にもシャドウを重ねる。瞳に映る女性の動作に伴い、画面の大半を占める目が変化し、大きく迫力のある目へとぐんぐん進化する。その勢いはあまりに鮮やかで、観る者が気付かぬうちに、独りでに静静と微妙な変化を遂げているのである。
しかし、ある時点から、魅力的か否か判別に困るようになる。瞳に映る人物が、目に留まらず他の部分をも黒で塗り始めるのだ。次第に黒は、顔に占める面積を広げ、終いには顔全体を飲み込んでしまう。
ここまですることは、「make up」と言えるのだろうか?と感じ、思わず辞書で「化粧」と調べた。広辞苑には「美しく見えるよう、表面を磨いたり、飾ったりすること」とあった。しかし、美しさの定義など、文化・国・性別・個人等々により異なるものである。顔面を漆黒に塗り尽くした姿を美しいと感じる人も存在するかもしれない。事実、日本でも、顔面を茶色で塗り、元の形が区別できないほどにパーツパーツに細工を施した姿を良しとする文化があるのだから、なかなかに化粧とは無限の広がりを持っているのであろう。そして、無限性をもつ「make up」を題材に、作品を「make up」しているところが、人々の関心を引き、展覧会そのものも可能性を感じさせるものとなった理由であろう。
(辻真理子)