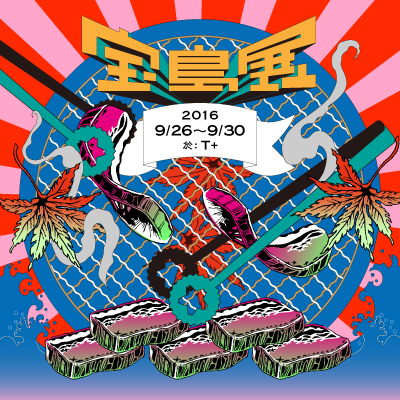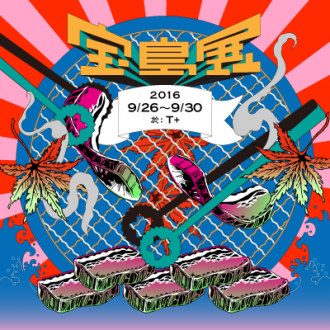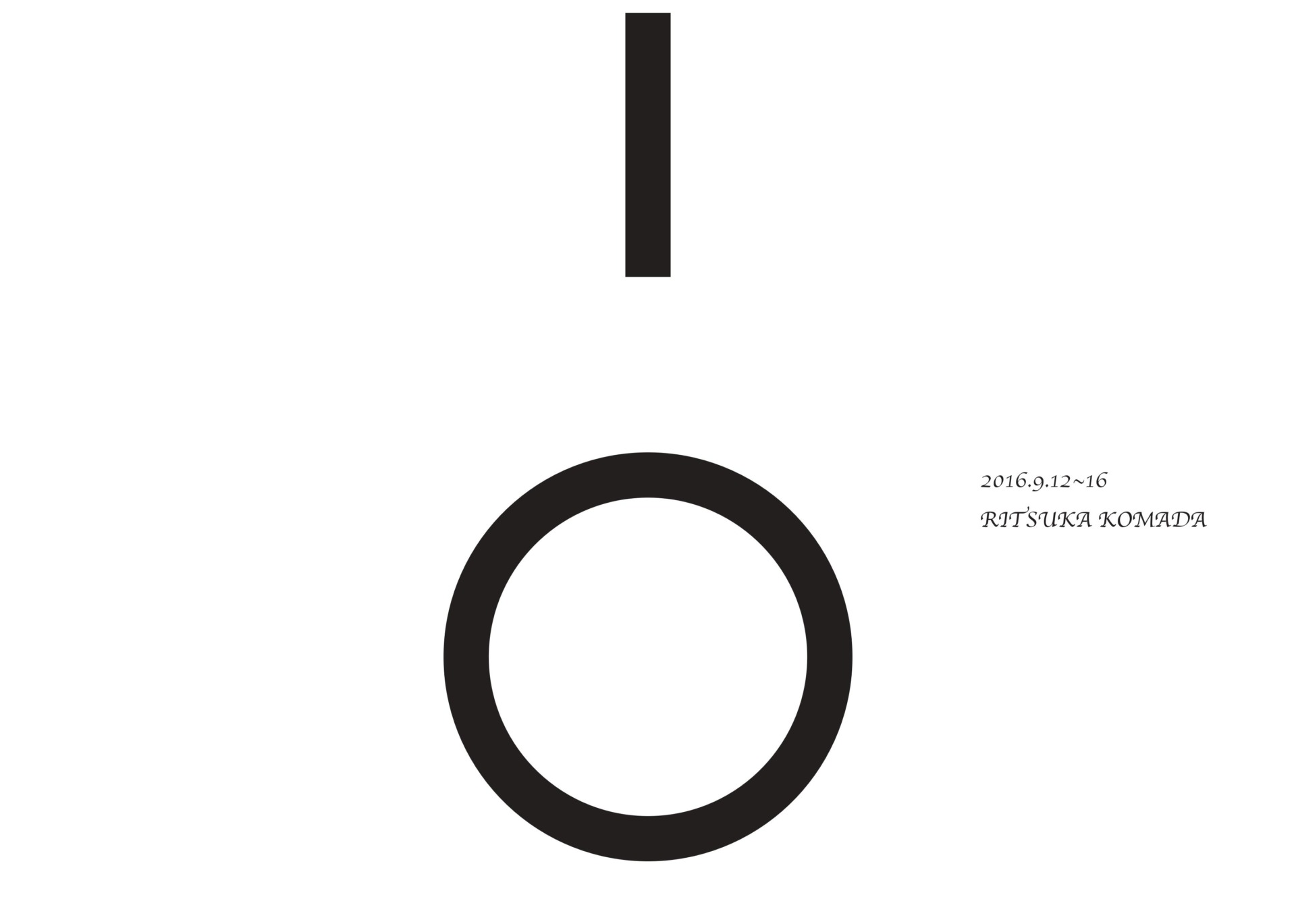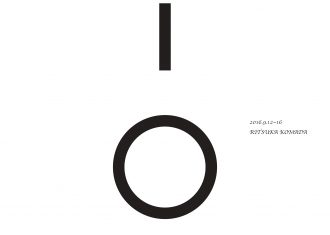「明後日が今日」坪坂萌 2016年10月25日~10月28日
会場:アートギャラリーT+
会期:2016年10月25日(火)~10月28日(金)
9:00~18:30
出展者:坪坂萌(人間総合科学研究科
芸術専攻洋画領域博士前期課程)
ドローイングの展示
T+review
壁一面が、ほとんどがモノクロの、ところどころにわずかな色を添えたドローイングで埋め尽くされている。その大きさはクロッキー帳の1ページから模造紙大まで幅広く、数枚の写真も交えて、どことなく混沌とした空間を作り出していた。
今回の展示を鑑賞しながら、自分がまるで作者の心象風景を覗いているかのような気分になった。断片的な少女たちの姿、どこかも分からない風景、白黒の空間…。ラフな描線と無造作な作品配置も相まって、整理の付かない不安定な様子であるという印象を受けた。黒く塗りつぶされた「明後日が今日」というタイトルも、差し迫った未来に対する恐れや不安感を表しているように感じ、作品を鑑賞しながら、複雑な感情の渦にのまれそうになった。
(戸田遥)