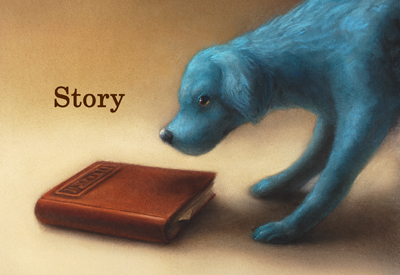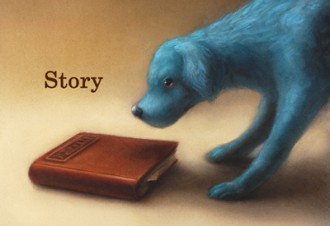「piece #2」 品川愛郁 2012年4月16日~2012年4月20日
会場:アートギャラリーT+
会期:2012年4月16日~2012年4月20日
出展者: 品川愛郁(美術専攻書コース4年)
書の小作品の展示
T+review
ギャラリーの中に、6点の書作品が並んでいる。形も色もすべてばらばらで、6点がそれぞれに個性的な額装をなされている。その見せかたでは、この限られたギャラリーという内の空間をみたすには統一感に欠けてしまうようにも思われる。しかし、不思議と混沌とした空気は感じられない。改めて作品達を見つめ、そして一点一点の作品に作者の対するこだわりを感じたとき、ギャラリー内全体が「書」を慈しむような空気に満ちていることに気付くのだ。
作品達は、そこに書かれている文字や文章に対して、効果的な大きさが選ばれている。また、文字が書かれている媒体の素材や、筆遣いなども使い分けられ、工夫されている。それらの、作品ごとに込められた複数の工夫が互いに効果を高め合い、文字の個性を強めている。
例えば、『桜』の文字は灰色に近い軽い色で書かれ、字の様子は風に舞う花びらのように動きにあふれている。また、『揮』は深いしっかりした黒い墨で、一画一画踏みしめるように力強く書かれている。朱色の紙に白い紙を乗せた上に書き、引き締まっている。
このような一点一点に対するこだわりから伝わってくるのは、作者が文字というものを無機質なものではなく、有機的で可能性のある表現の要素として捉えているような姿勢だ。作者は日本語というものを大切にして、真摯に向き合っているのだろう。作者にとって文字は、ただ情報を伝えるためだけの記号ではない。伝えている意味情報ばかりに目が向きがちな文字というものを、それ自体が独立して個性を持ちうるものに作者は仕立て直す。
文字というものに愛情をもって向かい合っている作者は、まるで文字たちの母であるかのように感じた。(岡野恵未子)