【活動紹介】日本デザイン学会秋季企画大会
11月17日、実践女子大学にて日本デザイン学会秋季企画大会が開催されました。学会各章授与式、基調講演、パネルディスカッションや学生プロポジション展示等があり、筑波大学・大学院からもデザイン専攻や感性認知脳科学専攻の学生、研究生ら5名が参加しました。学生プロポジション展示では、60名近い学生の研究や作品を観ることができました。展示中は常に発表者がポスターの脇に立ち、プレゼンテーションを行っていました。自らの研究について展示をした学生からは「初めは緊張もあり、なかなか相手に上手く話を伝えられなかったが、プレゼンテーションの回数を重ねるうちに要点をまとめて話せるようになってきた」「プレゼンテーションを行い、質問を受けたり、他の人の意見を聞いたりすることで、自分の研究についてより深く考えることができた」「様々な分野、視点からの研究が並び面白かった」といった感想を聞くことができました。
また、Kun Pyo Lee氏、浅香 嵩氏による基調講演、山崎 和彦氏、有吉 司氏、田中 浩也氏、中川 聰氏、高橋 義則氏によるパネルディスカッションも行なわれました。いずれも、これからのデザインについて考えるための良い機会となったと思います。
「良いものを皆に」供給するための大量生産の時代、私たちは満足と同時に不安を得ました。大量生産の時代は、ユーザー像の平坦化、作る人と使う人の分離、大量消費による大量のゴミを生んできました。「新世紀になって始めの10年は前世紀をひきずる」と言われるように、2012年も終わろうとしている今、20世紀的な考え方から切り替わる時期にあります。これからは、すでにあるものを、うまく使う時代でしょうか。また例えば、家庭用プリンタが普及したように、3Dプリンタの普及が期待されています。これが示すのは、アイディアさえあれば誰もが簡単に「ものづくり」に参加できる時代。製品が「小さな工場」でできるのなら、市場の規模を小さくし、限定されたユーザーコミュニティの中で柔軟に展開させていくことも簡単になります。壊れた製品のパーツも、3Dプリンタを使って簡単に出力できるため、個人でも簡単に修理ができるようになります。そこでいかに修理するか、「リペアのデザイン」が発達する時代。…様々な可能性が広がりますが、どれもこれからのデザインや製品の在り方の一つでしょう。他にも印象的なお話が多々ありました。自分よりもすごい、と思える人に出会って圧倒されることもよくあります。ただしそこで真に理解していくには時間が必要であり、話していくと本当にすごいところも、改善点も冷静に見ることができるようになるのだということ。常に小さなイノベーションを重ね、新しい道を行くことが大切であるということ。……
来春5月の同春季大会は、筑波大学で開催される予定です。新しい考えとの出会いを楽しみにしています。[デザイン専攻4年 M.I]
また、Kun Pyo Lee氏、浅香 嵩氏による基調講演、山崎 和彦氏、有吉 司氏、田中 浩也氏、中川 聰氏、高橋 義則氏によるパネルディスカッションも行なわれました。いずれも、これからのデザインについて考えるための良い機会となったと思います。
「良いものを皆に」供給するための大量生産の時代、私たちは満足と同時に不安を得ました。大量生産の時代は、ユーザー像の平坦化、作る人と使う人の分離、大量消費による大量のゴミを生んできました。「新世紀になって始めの10年は前世紀をひきずる」と言われるように、2012年も終わろうとしている今、20世紀的な考え方から切り替わる時期にあります。これからは、すでにあるものを、うまく使う時代でしょうか。また例えば、家庭用プリンタが普及したように、3Dプリンタの普及が期待されています。これが示すのは、アイディアさえあれば誰もが簡単に「ものづくり」に参加できる時代。製品が「小さな工場」でできるのなら、市場の規模を小さくし、限定されたユーザーコミュニティの中で柔軟に展開させていくことも簡単になります。壊れた製品のパーツも、3Dプリンタを使って簡単に出力できるため、個人でも簡単に修理ができるようになります。そこでいかに修理するか、「リペアのデザイン」が発達する時代。…様々な可能性が広がりますが、どれもこれからのデザインや製品の在り方の一つでしょう。他にも印象的なお話が多々ありました。自分よりもすごい、と思える人に出会って圧倒されることもよくあります。ただしそこで真に理解していくには時間が必要であり、話していくと本当にすごいところも、改善点も冷静に見ることができるようになるのだということ。常に小さなイノベーションを重ね、新しい道を行くことが大切であるということ。……
来春5月の同春季大会は、筑波大学で開催される予定です。新しい考えとの出会いを楽しみにしています。[デザイン専攻4年 M.I]
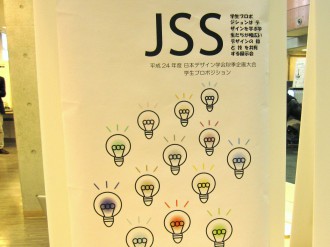
ひらめきの集まる場所
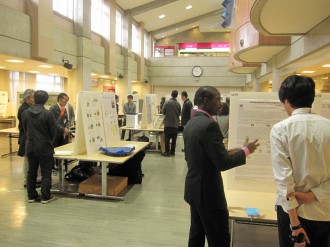
学生プロポジション展示の様子

講演の様子。壁にはポイントをまとめたポストイットが。



