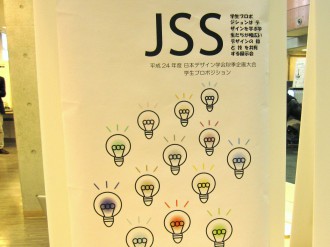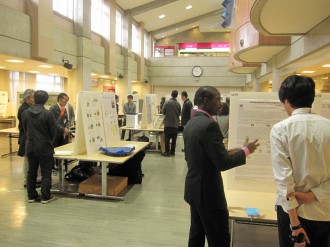【行事紹介】ふいご祭
11月23日、芸術学系棟工房にて「ふいご祭」が開催されました。この行事は、ものづくりを学ぶデザイン専攻の皆の安全と成長を感謝・祈願するために、毎年行われています。例年3年生が主体となって、デザイン専攻の学生や先生方、OB・OGの方々などを招待したり、懇親会の幹事や準備をしたりしています。昨年度は幹事側だった私たち4年生も、今回は気楽に楽しませていただきました。
また、毎年3年生の中から選出されることがお馴染みとなっている「神主さん」役ですが、今回は新しくプロダクトデザイン領域の先生となられた山田先生が神主役に。
儀式が終わると、次は懇親会です。今年は大学会館レストランの「プラザ」が懇親会の会場だったので、歩いて移動することができました。立食形式で、テーブルにはパスタやおでん、サンドイッチなどが並びます。五十嵐先生による乾杯の音頭で、懇親会が開会されました。
会場内は、OB・OGの方々との久々の再会や、新たな出会いで盛り上がっていました。私も、お世話になった先輩方と久々にお会いしました。仕事のこと、大学院のこと、思い出話…いろいろな話が浮かびます。お話している間、先輩方がご在学されていた日々を振り返り、懐かしく思いました。それと同時に、それぞれの場所でご活躍されている先輩方のお話しぶりから、時間が経ったなと実感しました。私達は1年後、どうなっているのでしょう…先輩方のように、ふいご祭で再会できる人はどれくらいいるでしょうか。企業に就職する人、学校の先生になる人、大学院に進学する人…。出身も進路もバラバラな私達は、大学を出るとなかなか集まることが難しいのだろうなと思いながらも、楽しい時間は過ぎていくのでした。
懇親会が終わり、参加できる人は2次会へと向かいました。悩んでいることについても、人に話せば思いがけずすんなりと道が開けることだってあります。いろんな人の話を聞いて、聞いてもらって、他愛のないことで笑って、ちょっと考え込む。こういった機会が実はすごく大事なのだろうなと思いました。
この日のために、時間をかけて準備をしてくれた3年生の皆さん、ありがとうございました。[デザイン専攻4年 M.I]
また、毎年3年生の中から選出されることがお馴染みとなっている「神主さん」役ですが、今回は新しくプロダクトデザイン領域の先生となられた山田先生が神主役に。
儀式が終わると、次は懇親会です。今年は大学会館レストランの「プラザ」が懇親会の会場だったので、歩いて移動することができました。立食形式で、テーブルにはパスタやおでん、サンドイッチなどが並びます。五十嵐先生による乾杯の音頭で、懇親会が開会されました。
会場内は、OB・OGの方々との久々の再会や、新たな出会いで盛り上がっていました。私も、お世話になった先輩方と久々にお会いしました。仕事のこと、大学院のこと、思い出話…いろいろな話が浮かびます。お話している間、先輩方がご在学されていた日々を振り返り、懐かしく思いました。それと同時に、それぞれの場所でご活躍されている先輩方のお話しぶりから、時間が経ったなと実感しました。私達は1年後、どうなっているのでしょう…先輩方のように、ふいご祭で再会できる人はどれくらいいるでしょうか。企業に就職する人、学校の先生になる人、大学院に進学する人…。出身も進路もバラバラな私達は、大学を出るとなかなか集まることが難しいのだろうなと思いながらも、楽しい時間は過ぎていくのでした。
懇親会が終わり、参加できる人は2次会へと向かいました。悩んでいることについても、人に話せば思いがけずすんなりと道が開けることだってあります。いろんな人の話を聞いて、聞いてもらって、他愛のないことで笑って、ちょっと考え込む。こういった機会が実はすごく大事なのだろうなと思いました。
この日のために、時間をかけて準備をしてくれた3年生の皆さん、ありがとうございました。[デザイン専攻4年 M.I]

今年もお祈りをします。

大学会館レストラン「プラザ」にて、乾杯!

おでんもありました