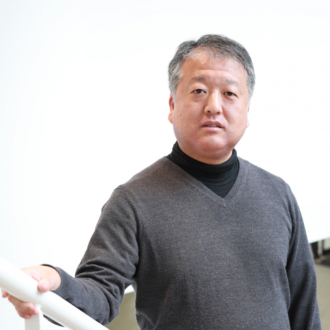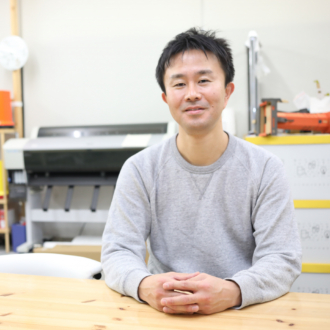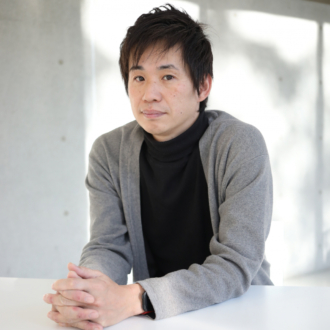伊藤 節
芸術系 教授
平成の30年間イタリアを中心にデザイン活動を展開してきました。ルネサンスから500年の時を経て人間中心の個の解、「差」を求める西欧思想の科学技術の発展は、ここに来て私たちの住む社会環境や自然環境に対し様々な環境破壊や、AI社会における人間性欠如の危機という歪みを生んできています。世界は今新型コロナウィルスによるパンデミックに揺れています。令和の時代が開けた今日、森羅万象を大切に考えるアジア、日本発の自然との共生、異なる分野間の協調、「和」の科学技術による問題解決力が求められます。その鍵を握るのは感性、情緒あるクリエイティビティ、人間性を発揮してバランスのよい問題解決の提案を行い、未来の社会生活を創造していくアート&デザインの力です。今後世界は2030年に向けたSDGs, ESGをはじめ、あらゆる人を受容するインクルーシブな社会のデザインと構築が極めて重要になってきます。私たちの研究室ではnature- centered と inclusive society をメインテーマに科学技術とアート&デザインが同時進行する新しい和のクリエイティビティを打ち出していきます。
小山 慎一
芸術系 教授
私たちの研究室では実験心理学的な手法や脳科学的な手法を用いて,デザイン・感性・消費者行動に関するさまざまな問題に取り組んでいます。視線追跡装置,筋電計,心拍計,fNIRS,fMRIなどの様々な計測装置を用いてユーザーの行動や心の動きを定量的かつ客観的に評価している点が特徴的です。今あるデザインの良し悪しを評価するだけでなく,現在のデザインの隠れた問題点を発見・解決し,未来の新しいデザインを創り出すことをミッションにしています。
李 昇姫
芸術系 准教授
Kansei Design LEELABは、1990年代、筑波大学で始めた「感性」の構造モデルを科学的に解明する基礎研究から出発し、現在は感性情報学、感性デザイン学を中心に人間と製品・ロボット・環境を繋ぐHCI(Human Computer Interface/Interaction)研究を展開しています。脳科学・工学・認知科学・心理学・生理学・情報学など多様な異分野研究領域との融合研究を基盤にした人間に“思いやり”を与えるデザインを創ります。人間の感性と行動プロセスを認知的エスノグラフィー理論と融合させ、人間の動作を美しく創造するデザインを目指します。オランダのデルフト工大、アイントホーフェン工大、イタリアのミラノ工大、韓国のKAIST、梨花女子大学校などと積極的な国際研究協力も行っています。
内山 俊朗
芸術系 准教授
私たちは日常生活の中にある遊びや楽しいことを探究し、ユニークで新しいアイデアを生み出し、新しい体験を創り出すことを研究のテーマにしています。研究室のメンバーはいずれも技術の専門家ではありませんが、新しいアイデアをハード、ソフトのプロトタイピングツールを用いて素早くカタチにし、実際に体験できるようにしています。実験や展示を通して、その体験が利用者にとって快適でわかりやすいものであるか検証、改善し完成度を高めています。このようなプロセスは驚きや喜びを届けるエンターテインメントをデザインする上で重要なプロセスであると考えています。また、私たちの力をより高度で大きなプロジェクトにも反映させるべく、工学分野とのコラボレーションも積極的に行っています。
山田 博之
芸術系 准教授
プロダクトを「コミュニケーションツール」の観点から捉え、対人コミュニケーションを円滑にするための様々なツールのデザイン・開発とその評価を行っています。ユーザーエクスペリエンスを評価軸としたアプリケーション開発のために、プロトタイピングと評価のサイクルによるアジャイルな開発を実践しています。
また、筑波大学発の9番目のベンチャーとして起業したロゴスウェア株式会社では、Eラーニングを中心としたプロダクトの開発を行っています。オンラインセミナーにおける配信システムの開発では、その成果物がベネッセコーポレーションのライブ授業システムや、株式会社マイナビのWEBセミナーシステムとして幅広く利用されています。
索米亜
芸術系 助教
人類最も偉大な二つの発明は科学と芸術だと信じています。その間で探索し研究するには、無限の楽しさがあります。我々は科学を通して世界を理解し、芸術を通して世界を感じます。しかし、科学は人類共通の理解と言っても過言ではないですが、芸術に関しては人々が共感しきれない場合が多いです。その間で探索するのはデザインです。デザイナーは芸術を通してデザインを実現しようとする時、人々に納得してもらえず、論理的な解釈が求められる場合が少なくありません。デザイン創造活動を支援するために、我々は科学的なアプローチで人間の感情、気分、愛着など、いわゆるこころの動き(感性)のメカニズムを解明し、理論的な研究及びデザインへの応用研究を行います。