
[ 大会ホーム | 大会メッセージ | 大会日程 | 研究発表 | 特別行事 |参加 | 学会]
研究発表
予定は変更になることがあります。
研究発表
予定は変更になることがあります。
 |
[ 大会ホーム | 大会メッセージ | 大会日程 | 研究発表 | 特別行事 |参加 | 学会]
|
|
研究発表
|
予定は変更になることがあります。 |
|
|
|
|
左をクリックしても何も起きないとき... |
研究発表一覧表 |
|||||||
| 室名 | 研究発表室1 | 研究発表室2 | 研究発表室3 | 研究発表室4 | 研究発表室5 | 研究発表室6 | 研究発表室7 |
| 室番号 | 52B11 | 53A02 | 53A03 | 53A11 | 53A12 | 53C11 | 53C12 |
| 座席数 | 240人 | 80人 | 80人 | 80人 | 80人 | 80人 | 80人 |
| 設備・機器 | スライド OHP ビデオ(VHSのみ) コンピュータ入力 |
スライド OHP ビデオ(VHSのみ) コンピュータ入力 |
スライド OHP ビデオ(VHS/8mm) |
スライド OHP ビデオ(VHS/8mm) |
スライド OHP ビデオ(VHS/8mm) |
スライド OHP ビデオ(VHS/8mm) |
スライド OHP ビデオ(VHS/8mm) |
3月26日(月) |
|||||||
| 12:15~12:45 |
52B11教室 開会行事
|
||||||
| 発表A-1 1:00~1:25 |
ものづくりと状況的行為 ─デザインプロセスにおける道具とコンテキスト─ 伊藤順(新潟県立高田農業高等学校) |
昭和初期手工教育の実際―岐阜県高山市での木工による手工教育を探る― 齊藤暁子(鳴門教育大学大学院) |
台湾の小・中学校九年一貫新課程における「芸術と人文学習領域」について 蔡惠真(筑波大学大学院) |
題材「世界の仲間を救え〜コラージュ技法によるポスター制作〜」の実践的研究 立原慶一(宮城教育大学) |
“絵綴り方活動”の持つ教育的意義について 上中良子(大阪薫英女子短期大学児童教育学科) |
幼児の「身体」観の現況について 鈴木美樹(福島学院短期大学) 渡辺晃一(福島大学) |
児童画の国際交換・昭和30年代―公文書による― 草尾和之(大阪府立桃谷高等学校) |
| 発表A-2 1:30~1:55 |
劉 素真(筑波大学大学院) |
具象絵画の行方 -写実技法の変遷から- 桶田洋明(鹿児島大学) |
中学校美術科における立体表現の可能性と教材化の視点 伊庭靖二(兵庫教育大学大学院) |
マルチメディアコンテンツ製作による鑑賞に関する考察 山田芳明(大阪教育大学教育学部附属平野小学校) |
―小学校入門期において― 西尾正寛(大阪教育大学教育学部附属平野小学校) |
「教材の不易と流行」ー児童の興味・関心を基軸にー 岩崎由紀夫(大阪教育大学) |
「意味の希薄化という問題」は芸術教育にいかなる課題を突きつけるのか? 島田佳枝(東京学芸大学教育学部付属小金井小学校) |
| 発表A-3 2:00~2:25 |
小学校における表現と鑑賞に関わる一考察 西村隆司(大阪教育大学大学院) |
美術科ポートフォリオ評価における認知的基礎理論 池内慈朗(福井大学) |
『芸術による教育』成立の背景―美術批評家リードの歩みを軸に― 山木朝彦(鳴門教育大学) |
造形美術教育体系カリキュラムの構築 その1 ー系統試案とアメリカの美術教科書の考察ー 降籏 孝(山形大学) |
映像メディアを活用した美術教育の展開とその可能性 〜構造としての「対話」を踏まえて〜 赤木恭子(横浜国立大学大学院) |
チェコの幼児の色彩好悪と表現 島田由紀子(東京福祉専門学校) |
目と手と心の美術ー身体感覚に気づかせ学習の基礎を定着する授業の編成ー 渥美廣剛(神奈川県厚木市立荻野中学校) |
| 発表A-4 2:30~2:55 |
クリストと子供の造形活動との接点についての一考察 橋本忠和(一宮町立三方小学校) |
教科書調査と教諭インタビュー:鑑賞教育への示唆と展望 白浜恵里子(東京国立近代美術館研究補佐員) |
総合学習単元における統合過程としての美術の方法について 松原雅俊(横浜市立上郷中学校) |
テクノカルチャーと美術教育 - バウハウス研究からの示唆 - 本村健太(岩手大学) |
佐藤昌彦(北海道教育大学函館校) |
イギリスの「アーツ・アンド・デザイン」と「デザイン・アンド・テクノロジー」の目標の考察 小泉 卓(聖徳大学) |
|
| 発表A-5 3:00~3:25 |
メディア・アートが美術教育に拓く地平―媒体・芸術・教育の交差から― 永守基樹(和歌山大学) |
家庭における幼児の描画活動の環境と母親の配慮 福井晴子(岡山大学大学院) |
埼玉県立近代美術館の教育普及の取り組み 古山剛索(埼玉県立近代美術館) |
中学校美術科における評価に関する一考察 町田廣泉(筑波大学大学院・東京都板橋区立板橋第四中学校) |
美的発達段階の測定方法を用いた鑑賞教育の評価 杉林英彦(筑波大学大学院) |
幼児期、‘自分らしい’描画様式(概念)の成立に至るまで 〜遊びの中の描画活動から見えること〜 栗山 誠(帝塚山造形絵画教室) |
|
| 発表A-6 3:30~3:55 |
美術教育におけるインターネット活用の意味 丁子かおる(筑波大学大学院) |
擬似空間の箱を使った遠近法指導の実践研究 伊藤裕貴(福井県立敦賀高等学校) |
視覚伝達手段としての「版画」 荒木久美子(福島大学大学院) |
水彩画を中心とした心像表現(image画)に関する一研究 金 聖淑(国立韓国教員大学校) |
総合学習先行校と茅ヶ崎市美術館の試み―「美術」を介しての出会い― 永原陽子(茅ヶ崎市美術館) |
高校生が感じるCG表現のリアル(授業実践から) 足立 元(奈良県立奈良高等学校・奈良教育大学大学院) |
小学校図画工作科における教育コードの分析についての一考察 小野浩司(福島大学大学院・福島県福島市立金谷川小学校) |
| 発表A-7 4:00~4:25 |
セプトと広がり― 宮脇 理(元筑波大学) 永守基樹(和歌山大学) |
戦後の美術科教科書における掲載作品の研究 −立体作品編− 山口喜雄(宇都宮大学) |
Emile et Simone Senceの美術教育実践 1970年代フレネ教育による美術教育の一例 結城孝雄(兵庫教育大学連合大学院) |
||||
|
4:45~5:45 |
52B11教室 特別研究発表 バウハウス再現授業[ヨハネス・イッテンのデッサン] 岡本康明・鈴木雅子・前村文博(宇都宮美術館) |
||||||
|
|
大学会館レストラン 懇親会 | ||||||
3月27日(火) |
|||||||
| 発表B-1 9:00~9:40 |
美術教育におけるアートセラピーの意味 阿部寿文(大阪女子短期大学) |
What is Visual Literacy?: 米国における鑑賞教育の在り方 徳 雅美 (カリフォルニア州立大学チーコ校) |
韓国の戦前における美術教育の制度と実態 張 東浩(筑波大学大学院) |
教員を目指す大学生の美術鑑賞学習に関する考え方についてー批判的思考力の育成を目指してー 中村和世(米国イリノイ大学教育政策学研究科) |
|||
| 発表B-2 9:45~10:25 |
C.G.ユングのアートセラピー論 寺澤節雄(静岡大学) |
美術教育実践における教師の<意識−規範・文化>とディシプリン 宇田秀士(奈良教育大学) |
美術館・学校・市民の連携−世田谷美術館「美術鑑賞教室」の報告 塚田美紀(東京大学大学院研究生、世田谷美術館非常勤学芸員) |
自然観と<生命>表現の変容IIー外界との関係を問う美術・総合演習の実践からー 磯部錦司(宝仙学園短期大学) |
高等学校芸術科美術における「彫刻」の現状と課題 森田耕太郎(筑波大学大学院) |
さわってみて いいきもち−幼児の触感覚と創造力- 斎藤 寛子(福岡教育大学大学院) |
高齢者と美術教育 今井真理(愛知教育大学大学院) |
| 発表B-3 10:30~11:10 |
韓国の近代美術教育と素描 高 敬來(東京芸術大学) |
教材としてのアート・ゲームの可能性と問題 ふじえ みつる〔愛知教育大学) |
西洋絵画の鑑賞指導――メッセージを読み解く―― 岡田匡史(信州大学) |
教育的線描論ーフォルメン線描と気質考ー 高橋文子(茨城大学大学院 水戸市立千波小学校) |
美術鑑賞学習の視点ーデューイの美的経験論を基底としてー 中村和世(米国イリノイ大学教育政策学研究科) |
吉田悦治(琉球大学) |
|
| |
|||||||
| 発表C-1 12:30~1:25 |
アートプロジェクト検見川送信所2000 長田謙一(千葉大学)・内藤ちなつ・坂本顕子・清水嘉子・ 妹尾知子・宮原裕美・中村喜代子・稲本竜太郎(以上千葉大学院生)本田悟郎・関圭一郎(以上千葉大学研究生) 森修・平岡紀子(委託研究生) |
美術教育史研究部会 | 「絵画制作学」研究 渡辺晃一(福島大学) |
||||
| 発表C-2 1:30~2:25 |
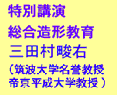 |
美術教育の課題と 授業研究部会 |
アートセラピー研究部会 |
||||
| 特別行事2:45~3:45 | |||||||
| 4:00~5:00 |
52B11教室 総会・閉会行事
|
||||||
| |
|||||||
| 室名 | 研究発表室1 | 研究発表室2 | 研究発表室3 | 研究発表室4 | 研究発表室5 | 研究発表室6 | 研究発表室7 |
| 室番号 | 52B11 | 53A02 | 53A03 | 53A11 | 53A12 | 53C11 | 53C12 |
|
|
|
|
左をクリックしても何も起きないとき... |